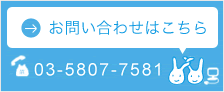HOME > ライブラリー > 旅する世界の保健室 > vol.19.ザンビア
- ライブラリー TOP
- シェアの書籍一覧
- 外国人医療相談ハンドブック
- 広報紙「SHARE LIFE」
- 旅する世界の保健室
- vol.1バングラデシュ
- vol.2ホンジュラス
- vol.3スーダン
- vol.4ガーナ
- vol.5インドネシア
- vol.6中国
- vol.7アフガニスタン
- vol.8東ティモール
- vol.9ウガンダ
- vol.10ソマリア
- vol.11ザンビア
- vol.12オーストラリア
- vol.13フィリピン
- vol.14日本
- vol.15日本
- vol.16ケニア
- vol.17ガーナ
- vol.18ベリーズ
- vol.19ザンビア
- vol.20東南アジア
- vol.21ホンジュラス
- vol.22ザンビア
- vol.23ケニア
- vol.24.日本
- vol.25.カンボジア
vol.19.ザンビア
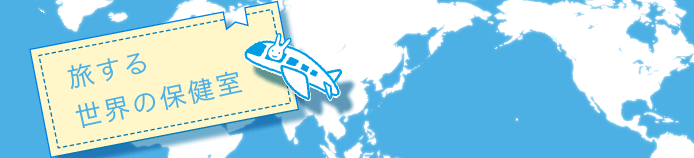
ザンビアの国境地域で「コミュニティーナース」として奮闘中
1.協力隊を目指したきっかけ
幼い頃にテレビで見た発展途上国の貧しい生活状況に衝撃を受け、漠然と国際協力に関心を持つようになりました。学生時代に参加したカンボジアのボランティアでは、発展途上国の生活の現場を見て、生まれた国や置かれた環境による格差を感じる一方で、貧しい状況にも関わらず住民は笑顔に溢れ、幸せそうに暮らしていた姿が印象的で、将来は青年海外協力隊としてそうした人々の中で活動したいと思うようになりました。看護師として臨床経験を積んだ後、国際保健をより深く学ぶためシェアのインターンを1年間経験し、感染症は予防出来るにも関わらず多くの人々の命を奪い、更には差別にも繋がるなど貧困問題と密接に関連することを学び、感染症・エイズ対策隊員として夢だった青年海外協力隊にチャレンジすることにしました。2.感染症・エイズ対策隊員としてザンビア共和国へ
私はザンビアの「カズングラ」という、世界にここ1つしかないザンビア・ボツワナ・ジンバブエ・ナミビアの4カ国の国境が接する地で、地域の保健・医療を担う地域ヘルスセンターで活動しています。このエリアは国境地域でトラックが越境のために滞留し、性産業従事者も多いことから、性感染症の感染率はザンビアの平均よりも高いだろうと言われています。活動先では、元々看護師をしていたこともあり「コミュニティーナース」という肩書きを頂き、地域とヘルスセンターの架け橋となること、そして健康教育を軸に活動に取り組んでいます。3.コミュニティーナースとしての、主な3つの活動
●地域の健康課題の視覚化ザンビアの各ヘルスセンターには、職員の他に「コミュニティーヘルスボランティア(CHV)」という各村から選ばれたボランティアがいます。一方職員は他地域から仕事で移住した人ばかりで人々の生活の様子をよく知りません。国境地域といえども、健康問題は各エリアの生活状況で異なります。住民の生活を知り地域に根ざした保健サービスを提供出来るよう、同僚やCHVと協力して地域の地図をつくり、水や電気の確保方法やHIV/AIDSの感染率の高い地域を地図に示し、生活状況や健康課題の視覚化に取り組んでいます。
●地域での健康教育
国境に近い地域は性感染症の新規感染が多い傾向があり、水道のない地域では川の水を直接飲むため子供の下痢が多く、物売りの仕事に従事する母親が多い地域では子供の栄養失調や予防接種を逃しているケースが多く見られます。性感染症の予防、手洗い、安全な水の確保、栄養そして予防接種の重要性等、自作のマテリアルを用いながら同僚やCHVと共に、地域住民に向けて健康教育を行っています。
●学校での健康教育
青少年が自ら健康を守ることが出来るようになることが重要であると考え、同僚やCHVと共に地域の学校に赴き健康教育を行っています。また、今後生徒同士で互いに学びあうことが出来るように、生徒の中から参加者を募りユースグループを各学校で結成しました。今後は彼らが楽しく健康について語り合う場を設けると共に、クラスメイトに彼ら自身がリーダーとなり、健康教育が出来るよう取り組む予定です。

4.今後の活動
2年間の青年海外協力隊としての活動も、そろそろ折り返し地点です。後半は活動を定着させ継続するために、いかにCHVやユースグループのモチベーションを保ち、活動を支えていくかが最大の課題です。ヘルスセンターの予算も限られているため、アイデアを凝らし活動資金を自分たちで確保していく必要があり、同僚と共に試行錯誤の日々です。今後も初心を胸に「コミュニティーナース」として地域に根ざして頑張っていきたいと思います。青年海外協力隊(感染症・エイズ対策)/元シェアインターン/看護師・保健師 野瀬 友望
機関誌「Bon Partage」No.162(2018年10月)掲載
機関誌「Bon Partage」No.162(2018年10月)掲載