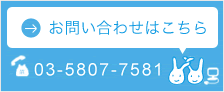HOME > ライブラリー > 旅する世界の保健室 > vol.14日本
- ライブラリー TOP
- シェアの書籍一覧
- 外国人医療相談ハンドブック
- 広報紙「SHARE LIFE」
- 旅する世界の保健室
- vol.1バングラデシュ
- vol.2ホンジュラス
- vol.3スーダン
- vol.4ガーナ
- vol.5インドネシア
- vol.6中国
- vol.7アフガニスタン
- vol.8東ティモール
- vol.9ウガンダ
- vol.10ソマリア
- vol.11ザンビア
- vol.12オーストラリア
- vol.13フィリピン
- vol.14日本
- vol.15日本
- vol.16ケニア
- vol.17ガーナ
- vol.18ベリーズ
- vol.19ザンビア
- vol.20東南アジア
- vol.21ホンジュラス
- vol.22ザンビア
- vol.23ケニア
- vol.24.日本
- vol.25.カンボジア
vol.14日本
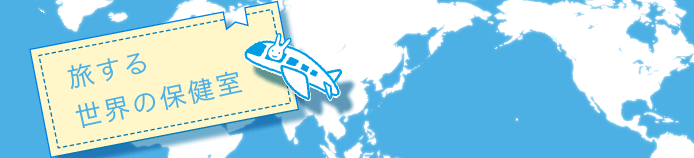
太平洋に浮かぶ南の島、42 年前の医療活動から
返還間もない小笠原診療所
東京から南へ1000キロ、約450年の歴史と豊かな自然が残る小笠原諸島。太平洋戦争中は島民全てが本土へ強制疎開、戦後はアメリカに統治され、1968年にアメリカから日本に返還。私は村づくりの復興計画が進む小笠原へ看護師として赴任することになりました。診療所は、アメリカ統治下に使われていた碧い海辺に建つ平屋の細長い木造の建物、診察室、治療室、手術室、薬剤室等があり、職員は大学の医局から2ヵ月交代の医師1名、看護師常時2名、放射線技師1名、事務1名、補助職員1名でした。
当時、島の人口は約1000人、患者は多い日で50~60人、島民の他に赴任職員、建築・土木業者、観光客などでした。多くは高血圧、心臓病などの循環器疾患、消化器疾患、アルコール依存などの精神疾患と事故による怪我でした。看護師は、診療の補助・処置、往診、健康指導と服薬指導、薬剤・機器・記録管理、役場との連携など多岐にわたり、内科、外科、皮膚科、小児科など全科に対応できる知識・技術が求められていました。
島唯一の医療機関で出遭った事
ある日、船員同士の喧嘩で腹部を切られた男性Kさんが運ばれてきました。15センチ程の裂傷から腸が出ていて、血圧は60以下に下がっている泥酔状態で啖呵を切り、体を触ろうものなら暴れ出すほどでした。あいにく医師も他の看護師も別の島に行っていて留守でした。とにかく救急処置をとらなければなりません。漁師仲間と村人と一緒にKさんを手術室まで運んび、暴れるKさんの体を押さえてもらい、先ずは血管確保、容態を見ながら、傷つき汚れた腸を生理食塩水で洗い、出血を止めるため滅菌ガーゼで抑える処置をとり、手術に備えて体を洗い、医療器具の準備をして医師の到着を待ちました。急ぎ到着した医師の判断で、傷ついた腸を吻合し人工肛門を造設をして手術は終了しました。術後の血圧は60~70台と低く危篤状態のため、病室に移し昼夜の看護が始まりました。
本土との距離、Kさんとの距離
このような重篤な患者の場合、自衛隊の飛行艇を依頼して本土の病院に搬送してもらうことになっていましたが、Kさんには前科がある上に、喧嘩での負傷という理由で飛行艇は使えず、一週間後の船で病院へ搬送されることになりました。Kさんの容態は日毎に安定し「酒もってこい」など悪たれを吐くようになり、「どうせ俺なんか生きている価値がない」と自己否定したり、血圧を測ろうとすると振り払おうとしたりしました。しかし、本土までは50時間かかる船旅、付き添いもいない、手作りの人工肛門装具の処置を自分でできるようにと叱咤しながら繰り返し教えました。そのうち「これまで俺は親身になって叱ってもらったことがないよ」と云うようになり、きつい表情だったKさんに柔らかな表情がみられるようになりました。島を離れる日、担架で船室まで送り「元気になったら今度は島に遊びに来てね」といって別れを告げると、Kさんは初めて涙を浮かべ「有難う」の言葉を口にしました。
それから1年半後のこと、診療所の前に日焼けした男の人が立っていました。私の顔を見るなり、「あの時は世話になっちゃって...」と云い、診療所の入り口にマグロを置いて、「あんたは命の恩人だ...俺は改心したよ...」と照れ臭そうに云い、手を振りながら波止場の方に向かっていったKさんの姿は、まるで人が変わったように力強い若者になっていました。
命を救うためとは云え、看護師としてやってはいけない医療行為、遠く離れた孤島で想像もつかない様々な事態に出会い、やらざるを得ない状況に置かれて、高度な医療設備が整い、スタッフも揃っている本土では経験できないことでした。置かれた場所で、人の命や生活を守ること、人として尊厳を考えさせられた時でもありました。
シェア火曜(通う)ボランティア、元看護師 上部恵美子
機関誌「Bon Partage」No.157(2015年10月)掲載
機関誌「Bon Partage」No.157(2015年10月)掲載