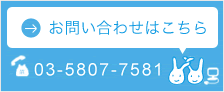HOME > ライブラリー > 旅する世界の保健室 > vol.13フィリピン
- ライブラリー TOP
- シェアの書籍一覧
- 外国人医療相談ハンドブック
- 広報紙「SHARE LIFE」
- 旅する世界の保健室
- vol.1バングラデシュ
- vol.2ホンジュラス
- vol.3スーダン
- vol.4ガーナ
- vol.5インドネシア
- vol.6中国
- vol.7アフガニスタン
- vol.8東ティモール
- vol.9ウガンダ
- vol.10ソマリア
- vol.11ザンビア
- vol.12オーストラリア
- vol.13フィリピン
- vol.14日本
- vol.15日本
- vol.16ケニア
- vol.17ガーナ
- vol.18ベリーズ
- vol.19ザンビア
- vol.20東南アジア
- vol.21ホンジュラス
- vol.22ザンビア
- vol.23ケニア
- vol.24.日本
- vol.25.カンボジア
vol.13フィリピン
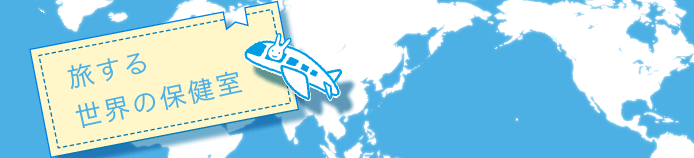
地域の健康を守る人を、地域で育てる
「住民による、住民のための健康を、その人たちとともに作りたい」
2014年1月、バンコクで開催されたマヒドン皇太子賞会議(Prince Mahidol Award Conference)の基調講演の終盤、登壇者の中で最年少のダイシリ・アイディルさん(20)が力強く宣言すると、会場は満場の拍手で応えました。ダイシリさんはフィリピン大学医学部レイテ分校を卒業したばかりの助産師で、同校の看護師課程に進級したところでした。しかし、彼女が通う校舎は2013年11月の台風30号で全壊し、授業再開の見込みが立たない状況でした。看護師として働く医師たち
フィリピンの保健医療は慢性的な人材の不足と偏在とに悩まされてきました。西洋化されたカリキュラムで病院中心の専門医療を学んだ医療者たちは、農村より都市で、国内より海外で働くことを望む傾向があり、全人口の半数以上が住む農山村を支える医療者は、全体の一割に過ぎません。また、国内で医師として働くよりも、海外で看護師として働くほうが高収入であることから、医師たちが看護師として頭脳流出する事態を招いています。こうした中で、類まれな成果を上げた医学校が、国立フィリピン大学医学部レイテ分校です。
プライマリ・ヘルス・ケアの聖地
レイテ分校は全校生徒が200人に満たない小さな学校ですが、1976年の創立以来3,351人の卒業生を送り出し、その90%以上がフィリピン国内にとどまって活躍するという成果をあげてきました。一番の特色は、地域全体で医療者を育てるカリキュラムです。入学試験は無く、授業料もかかりません。それぞれの出身地域から推薦された学生たちは、まずはコミュニティーヘルスワーカーとして助産の技術を学び、地域実習で経験を重ね、地域の人々に育てられます。地域の人と共に生活し、その人々を取り巻く健康課題を抽出し、そこにある資源を用いて、そこに住む人々と健康課題を解決していく、まさにプライマリ・ヘルス・ケアの実践そのものを学ぶ学校です。
修了後はそれぞれの地域に派遣をされ、地域の人々に働きぶりが評価されると、次は看護師の過程に進学することができます。その後の保健師、医師と続くカリキュラムの各段階も同様です。
地域で人を育てる
冒頭の会議の一週間後、私とダイシリさんは、レイテ島タクロバン市で再会しました。スーツからTシャツに着替えた彼女は、同級生や教員たちとともに仮設校舎の屋根を運びながら、笑顔でこう続けました。「台風になんて負けていられません。私たちは自分の出身地に戻って働くのを誇りに思うし、それが一番の喜びです」
レイテ分校の人づくりの秘密は、生徒たちが地域の中で学び、育てられ、その地域の一員として役割を担っていることです。地理的・社会的へき地で健康を守る人を、どう育て、どう定着させるか、私たちがレイテ分校から学ぶべきことが大いにあるのではないでしょうか。

写真:自分たちの手で仮設校舎を建てる生徒たち(2014年2月、レイテ島)
レイテ分校設立にあたり、佐久総合病院の故・若月俊一院長が唱えた「農村医科大学」構想が大きく影響を与えたとされ、同校と当院とは長く人の交流を重ねてきました。台風30号の復興支援のために当院が呼びかけた「レイテ分校友の会」では、2014年9月までに二度の現地調査団を派遣し、シェア会員の皆様をはじめ日本全国の支援者から寄せられた総額500万円余りの支援金を送金し、仮設校舎建設と授業再開を後押ししました。皆様のご支援に改めて感謝を申し上げます。
2014年12月10日の台風被害により、レイテ分校仮校舎が半壊しました。再度寄付のお願いを開始しています。ご協力くださる方は、レイテ分校友の会facebookの情報の確認をお願いします。
2014年12月10日の台風被害により、レイテ分校仮校舎が半壊しました。再度寄付のお願いを開始しています。ご協力くださる方は、レイテ分校友の会facebookの情報の確認をお願いします。
レイテ分校友の会 佐久総合病院総合診療科 座光寺正裕
機関誌「Bon Partage」No.156(2014年11月)掲載
機関誌「Bon Partage」No.156(2014年11月)掲載