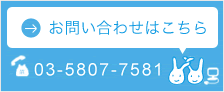HOME > ライブラリー > 旅する世界の保健室 > vol.3スーダン
- ライブラリー TOP
- シェアの書籍一覧
- 外国人医療相談ハンドブック
- 広報紙「SHARE LIFE」
- 旅する世界の保健室
- vol.1バングラデシュ
- vol.2ホンジュラス
- vol.3スーダン
- vol.4ガーナ
- vol.5インドネシア
- vol.6中国
- vol.7アフガニスタン
- vol.8東ティモール
- vol.9ウガンダ
- vol.10ソマリア
- vol.11ザンビア
- vol.12オーストラリア
- vol.13フィリピン
- vol.14日本
- vol.15日本
- vol.16ケニア
- vol.17ガーナ
- vol.18ベリーズ
- vol.19ザンビア
- vol.20東南アジア
- vol.21ホンジュラス
- vol.22ザンビア
- vol.23ケニア
- vol.24.日本
- vol.25.カンボジア
vol.3スーダン
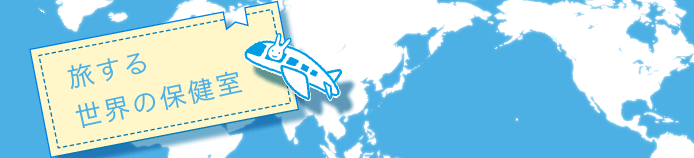
内戦終結5年目の南部スーダンの保健医療事情」
「南部スーダンで働くNGOに期待することはなんですか?」
「ハードワークです」
アフリカ・南部スーダン全10州のひとつ、東エクアトリア州の保健大臣フローレンス・ナイティー氏は、私と同じNGOで働く同僚の問いにこう答えました。
「われわれの努力はまだ足りませんか?」
「ご覧の通り、東エクアトリア州は広大で、地方に住む人々も多いです。『難民を助ける会』がロパ郡で3つの簡易診療所の運営をサポートしているのには感謝しますが、それでも医療サービスを受けられる人は南部スーダン全体をみれば4分の1にすぎません。いっそうの努力を期待します」
22年に及ぶ内戦で保健医療施設も破壊され、医療サービスを担う人材も絶対的に不足している南部スーダン。難民として隣国のウガンダ・ケニア・エチオピア・エジプトなどへ逃れていた人々のうち、これまでに約30万人が帰国、祖国の大地で新しい生活を始めつつあります。しかし内戦終結5年目の今日、子どもの予防接種率はたった5%(日本はほぼ100%)、5歳未満児死亡率は1000人あたり135人(日本は4人)、妊産婦死亡率は10万人あたり2054人(日本は4.4人)、安全な水を利用できる人口の割合は、人口の約3割にすぎません。また2006年に難民を助ける会が居を構えるカポエタという地域で行なった調査では、一人あたり一日の水使用量は2.5リットル(日本は307リットル)でした。舗装道路は、首都ジュバを除き、ほとんど皆無です。
南部スーダン人民解放軍の元最高司令官であり、2005年1月の包括和平合意調印後、スーダンの第一副大統領に就任したジョン・ギャランの口ぐせは、"bringing town into villages"(「村々に町を持ってこよう」)であったといいます。しかしようやく平和を手にいれて国づくりを始めたこの地では、医薬品を運ぶ車にさえ事欠き、例えば東エクアトリア州の人口160万人に対して医師は14名足らずと、先の州保健大臣が力説するように、NGO抜きには医療サービスを維持していけない現状があります。
この南部スーダンでは、129のNGOがなんらかの保健プロジェクトを実施しています。医療スタッフを雇用して保健施設を直接運営するNGOもまだ多いのですが、私たちのサポートする3つの診療所は現在のところ、地域保健員(Community Health Worker)と呼ばれ、保健省が給料を支払う有給スタッフと、地域保健ボランティア(Community Health Volunteer)と呼ばれる無償のスタッフで運営されています。われわれの役目は、医薬品が途切れないように、州保健省の倉庫から診療所までの医薬品の搬送をサポートすること、そして診療所で働くスタッフと共に、医療サービスの内容を向上させること、またこれら診療所を利用する地域の人たちに、自らの健康を守る働きかけを、地域保健員やボランティアの人々を通して行なうことです。
ロパ郡ロミン診療所を運営するベテランの地域保健員ジブデオさん。彼は月曜日から土曜日まで、毎朝7時半に診療所を開け、夕方5時半まで外来患者を診る働き者です。2009年1月の診療所の統計をみると、外来患者数は342名で、最も多かった疾患はマラリア(76)、次に外傷(65)、下痢(62)、かぜ(57)、目の感染症(30)と続きます。外傷が多いのは、この地域では木に登って食料になる実を取る時に落ちて怪我をしたり、牛の取り合いの過程で銃に撃たれることもままあるからだとか。
途上国と呼ばれる国の地方によくみうけられる共通の課題はここにもあります。医療施設まで歩いて何時間もかかること、携帯電話も、もちろんEメールもなく、町にある病院と連絡を取る手段がないので、急病人が出ても救急車を呼べないこと、そして街の病院ともし連絡が取れても、未舗装の道もでこぼこで狭く、雨季にはなくなってしまうような道路なので、救急車に来てもらえないこと、女性が毎日働かなければならないことなどから、子どもを病院に連れていくのが遅れがちになり、治療が手遅れになってしまうこと。
村に町を持ってくることはできなくても、村にいる人たち自身で村の診療所を中心になんとか人々の健康を守っていけないか、私たちは一日ずつの努力を重ねています。
元シェア東ティモールスタッフ 名取郁子
機関誌「Bon Partage」No.144(2009年7月)掲載
機関誌「Bon Partage」No.144(2009年7月)掲載