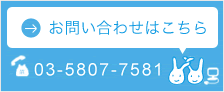HOME > ライブラリー > 旅する世界の保健室 > vol.2ホンジュラス
- ライブラリー TOP
- シェアの書籍一覧
- 外国人医療相談ハンドブック
- 広報紙「SHARE LIFE」
- 旅する世界の保健室
- vol.1バングラデシュ
- vol.2ホンジュラス
- vol.3スーダン
- vol.4ガーナ
- vol.5インドネシア
- vol.6中国
- vol.7アフガニスタン
- vol.8東ティモール
- vol.9ウガンダ
- vol.10ソマリア
- vol.11ザンビア
- vol.12オーストラリア
- vol.13フィリピン
- vol.14日本
- vol.15日本
- vol.16ケニア
- vol.17ガーナ
- vol.18ベリーズ
- vol.19ザンビア
- vol.20東南アジア
- vol.21ホンジュラス
- vol.22ザンビア
- vol.23ケニア
- vol.24.日本
- vol.25.カンボジア
vol.2ホンジュラス
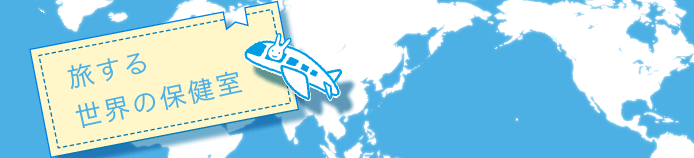
中米の国ホンデュラス―マティズモに苦しむ女性たち―
中米の小国
ホンジュラス共和国は、中米のほぼ中央に位置し、西はグァテマラとエル・サルヴァドル、東は、ニカラグアと国境を接しており、北はカリブ海、南は太平洋に面している。その首都は、テグシガルパであり、スペイン艦隊が中南米を制圧した時には、銀の鉱山として栄えたと言われている。
標高が1000メートルと、一年中クーラーも要らないほどよい気候であり、住むのに良い場所である。
ホンジュラスには、アメリカ資本によるバナナの巨大プランテーションが有名であり、日本でも有名なドールバナナはここから運ばれる。主な輸出品は繊維製品、コーヒー、バナナ、エビ、パーム油であり、日本へはコーヒーが主なものである。
夫婦の統計をみると正式な教会での結婚をしているのが50%、同棲という形の社会的な結婚が40%、そして残り10%が独身である。そして、いずれも子どもを持っているのがホンジュラスである。
マティズモとは
中米の多くの国の傾向であるが、ここでは、正式の結婚をしないで子どもを産むことは特別では無い。一見、ラテン系の世界であり、女性と男性は平等であると思われており、社会進出している女性も多く、通常の会話でも、好きな事をいっているように見える。
しかしながら、中南米には、マティズモという男性優位の考えがあり、それは特に地方で強く、女性は酒を飲んだり、タバコをすったりするのは、男と違いよくないと考えられているし、家庭内では男性優位で、文句を言えないという状態である。
また、キリスト教でありながら、結婚形態も正式に届出をしているのは、50%といわれている。実際は社会的に結婚し、皆、子どもがいるにもかかわらず、正式には届出をしていないのである。特に東部のオランチョ県では、拳銃片手に、牛を相手に暮らしているオランチョの男どもは、付き合った女性には子どもをつくることが男の証と考える。女性たちも非常に従順である。授けられた子どもを産み、その子を育てる。中絶はキリスト教で禁じられている事もあるが、授かった子どもは産むべきであると多くの女性は考えているし、付き合っている男性が去ったあとも、自ら子どもを育てる。身勝手な男たちは、次の女性へと走る。現地の言語(スペイン語)でムヘリエゴ(女たらし)という言葉があり、多くの女性、多くの子どもを持っている男どものことを言う。ただ、かれらの話を聞くと、女性蔑視とか、個人の問題というよりもこれまでの習慣も含めた文化の問題とも思えてくる。単に男性の問題というより、文化・歴史の問題であるかもしれない。
家庭分娩
 ホンジュラスには18の県があるが、いまだ家庭分娩が60%のオランチョ県、通常は伝統的産婆さんにお産の介助を頼む。
ホンジュラスには18の県があるが、いまだ家庭分娩が60%のオランチョ県、通常は伝統的産婆さんにお産の介助を頼む。日本の昔の産婆さんのように面倒見がよく、産後の世話、生まれた赤ちゃんの世話もしてくれる。
ただ、お産小屋といわれる建物や産婆さんの自宅での分娩であり、不清潔であり、お産後の感染の原因ともなっている。伝統的産婆さんの手に負えない時は、県病院に運ばれる。電話も村にはなく、舗装されていない道端にたち、通る車に手紙を託す。緊急の場合には、間に合わない事も多いと言われ、妊産婦の死亡が多いのも女性にとっての大きな課題である。
そんな人口40万人の県であるが、ここには日本の、無償資金協力で建設された100床の県病院(サンフランシスコ病院)があり、多くの住民の需要に答えている。山奥の村を訪れても、この病院の事を知らない人はなく、日本の援助が大変役にたっている事が実感される。40万人の県にたった一つの病院、手術ができるのはこの病院だけである。
写真:日本の無償資金協力で建てられた100のベッドの地域病院。医師を診断を待つ女性たち。
最後に
そんな女性が苦しんでいるホンジュラスだが、半面、保健医療分野の職員の半分以上は女性が占めている。マティズモの中、パワフルな女性らを見ていると将来の事を考え、日本と同じように女性パワーを感じ、心躍る国でもある。
シェア理事 仲佐保
機関誌「Bon Partage」No.143(2009年3月)掲載
機関誌「Bon Partage」No.143(2009年3月)掲載