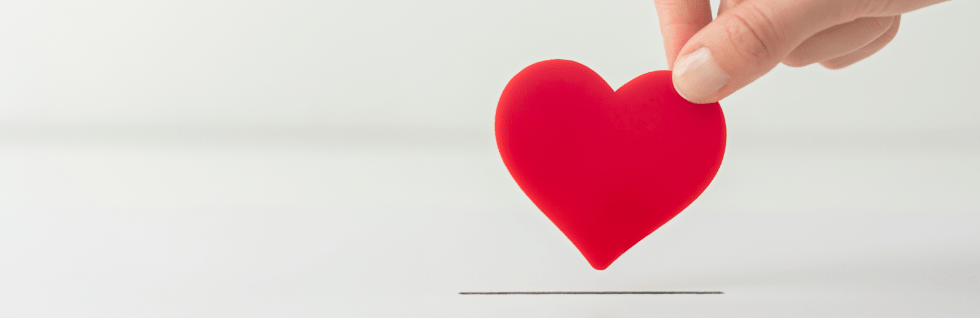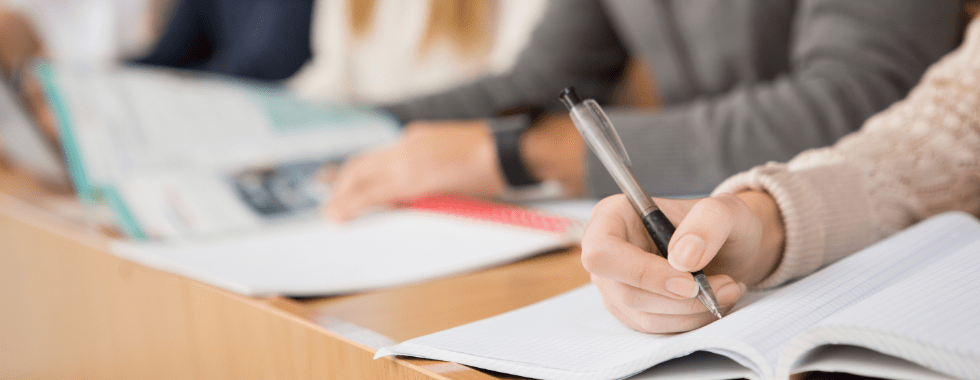東ティモールにおける国際保健活動
すべての妊産婦さんが安心して
受けられる保健医療サービスを実現する
東ティモールでは医療機関にかかることが難しく、妊娠や出産で命をおとす女性や赤ちゃんがいます。シェアは必要な保健医療サービスを住民に届けられるよう、公的医療機関で働く医療者の知識・技術の改善や、保健行政の強化を進めています。また参加型の保健教育活動を地域住民や学校とともに行うことで、自分たちの健康を自分たちで守れるようサポートしています。
活動中のプロジェクト
-

母子保健サービス活性化プロジェクト
東ティモールの首都ディリ県メティナロ郡とアタウロ特別県は、山に囲まれた地域で、母親と子どもたちが基本的な母子保健サービスへのアクセスに苦労しています。交通の問題、医療サービスの質の低さ、そしてコロナ禍の影響が、地域の健康状態を悪化させています。私たちシェアは、国際保健の一環として、地域社会と連携し、住民が母子保健サービスを利用できるよう地域社会と連携して活動しています。
-

思春期リプロダクティブヘルス啓発プロジェクト
首都ディリの人口密集地であるドン・アレイソ郡では、中高学校や学生が集中しています。性教育と思春期保健の提供は限定的であり、望まない妊娠や新生児遺棄の問題が新聞で取り上げられています。これらの問題は、思春期の生徒たちが妊娠・出産のリスクや教育機会の喪失に直面する原因となっています。私たちシェアは、学校や保健センターと協力し、性教育と思春期保健の改善に取り組んでいます。