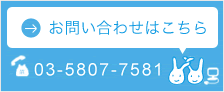- 基礎知識 TOP
- 国際保健
- プライマリ・ヘルス・ケア
- 公衆衛生
- エイズ
- HIVとAIDS
- 世界のHIV感染状況
- あるHIV陽性者の手記
- エイズのキーワード
- エイズ関連リンク
- 感染症
- COVID-19リリース
- COVID-19(1)
- COVID-19(2)
- COVID-19(3)
- COVID-19(4)
- COVID-19(5)
- COVID-19(6)
- COVID-19(7)
- COVID-19(8)
- COVID-19(9)
- COVID-19(10)
- COVID-19(11)
- COVID-19(12)
- COVID-19(13)
- COVID-19(14)
- COVID-19(15)
- COVID-19(16)
- COVID-19(17)
- COVID-19(18)
- COVID-19(19)
- COVID-19(20)
- COVID-19(21)
- COVID-19:新型コロナウイルス感染症の予防接種(ワクチン)について
- COVID-19(multi-language)
- COVID-19対策:妊婦の方々へ(多言語)
- 在日外国人の健康
- 在日外国人の健康(1)
- 在日外国人の健康(2)
- 在日外国人の健康(3)
- 在日外国人の健康(4)
- DVと在日外国人
- 地域リハビリテーション
- マイクロティーチング
- デビッド・ワーナー
- MDGs
- DOTS
- リプロダクティブ・ヘルス
- TBA
- 栄養
- 微量栄養素
- 緊急援助(国際・日本)
- 災害医療
- PTSD
- 野宿者
- 野宿者(1)
- 野宿者(2)
- 野宿者(3)
- 野宿者(4)
野宿者(1)
1990年代後半経済不況に伴い、一般の会社員や住み込み勤務の人々が、リストラによる生活破綻や希薄な家族関係により、いきなり野宿生活者になるというケースが頻繁に見られるようになり、急激に増加した野宿者が社会問題となった。野宿=住所不定となることは、地域住民でなくなることを意味し、さまざまな行政サービスや社会保障を受けられなくなる。例えばアパートの家賃を払えなくなり野宿生活になったとたんに、居所不明で生活保護を受けられなくなるという事態におちいるのである。
人間が心身共に健康な生活をおくるためには次の5つの条件がそろわねばならない。
(1)衣・衛生的な衣服
(2)食・栄養バランスのとれた食事
(3)住・厳しい気候をさけ健康を保つことが出来る住居
(4)安全・暴力から身を守ることが出来る環境
(5)希望・社会から疎外・排斥されず、将来に希望を持てること
これらの条件が自分自身で獲得できないという点で、野宿者問題と難民問題は同次元の問題であり、野宿者とは経済的な国内避難民と考えることができる。即ち、難民救援と野宿者支援は同じ視点に立って活動を行うことが出来るのである。国際協力に興味を持つシェアのボランティアの多くが、野宿者支援活動に協力を続けていることは以上のような理由があると考えている。難民に対しては、国連・NGOなどの国際援助機関が衣・食・住・安全を保障し、世界から注目を受けるが、野宿者にはごく小規模の支援団体が不十分な食料を提供することしかできず、その他の支援がほとんど無いのが現状である。野宿者は難民より悲惨な生活を強いられていると言えるのである。
野宿者の平均年齢は50代であり、45歳から65歳未満が大多数を占める。主に現場での肉体労働を長年続けており、経済不況の影響を最も大きき受ける人達である。また生活習慣病発症年齢層でもあり、多くが高血圧・糖尿病・胃潰瘍に罹患しているため、野宿生活自体がこれらの基礎疾患の悪化要因となっている。野宿者の平均死亡年齢は新宿や大阪での調査では50代後半であり、結核罹患率は一般住民の数十倍に達し途上国と肩を並べている。先進国であるはずの日本の都会の一角に健康指標が途上国と同じレベルの集団がおよそ2万人存在するのである。

このような野宿者の現実に対し、公衆衛生や保健行政関係者の関心が高いとは言えない、かつ福祉行政との連携もうまくとられてはいない。過去12年野宿者支援活動を行ってきた自分が、みなさんにアピールするため、ボン・パルタージュの紙面を借りて野宿問題をシリーズでお届けします。
【アオカン】:野宿の意、青空簡易宿泊所の略。明治時代の東京市の社会調査に、野宿することを「オカンする」という表記がある。青空+オカン=アオカンと思われる。
【アブレ】:失業の意。日雇い労働者が職にあぶれたときに使う。
【エサ拾い】:ゴミ箱などで残飯をあさること。
【越年越冬闘争】:年末年始期は仕事や店舗が長期間休業する。そのため、日雇い労働の賃金がなく、かつ飲食店からの残飯もなくなり、福祉事務所の対応もなくなる。野宿者にとって寒冷な気候もあり、非常に生き延びることが困難な期間である。そのため支援団体ではこの時期に合わせて、重点的に炊き出しや夜回り活動を行い、野宿者の健康維持を図っているところが多い。「闘争」は厳冬期を生き抜くための戦いの意。
【顔付け】:日雇い労働者が手配師を通さずに、直接過去に雇われた経験があるなどなじみの職場に雇われること。
【片づけ(仕事)】:建設現場での雑用や清掃などの軽作業。
【狩りこみ】:野宿者が野宿状態から半強制的に施設などに収容されること。
【ケタ落ち】:賃金・技術などの程度が低いこと。ケタ落ち職場、ケタ落ち病院など。
【シノギ】:路上強盗、マグロと同義。
【(日雇い)職安】:公共職業安定所労働課の出張所のこと。寄せ場にあり日雇い就労紹介とアブレ手当の支給が主な業務である。
【炊き出し】:民間の野宿者支援団体、宗教団体(キリスト教関係団体が多い)による、定期的な食糧配給。おにぎり、カレー、どんぶりなど様々だが、圧倒的に炭水化物が多く、野菜は少ない。山谷では諸団体が行っておりほぼ毎日あるが、新宿では全部あわせても週3回程度。配給に余裕があるときはお代わりなど食いだめをすることがある。
【ダンボール村】:1994年から1998年にかけて都庁への地下通路から新宿西口地下広場に集中したダンボール製の小屋群。多いときには200軒を超えた。
【チケット並び】:コンサートや野球などの前売り券を買う仕事。
【手配師】:労働者に仕事を紹介(「手配」)し、業者から紹介手数料を得ることを生業とする者。暴力団関係者もおり、寄せ場・駅・公園などで労働者に声をかけるが、低賃金など悪条件のところが少なくない。
【当事者】:野宿当事者。支援者と対比する意味
【特診券】:特別診療券。社会福祉法人の病院では、生活困窮者に対し無料・低額診療を行っている。福祉事務所がその券を預かり、来所者の中で簡単な治療を希望する人、生活保護を必要とするかどうかの鑑別診断などの目的で交付している。
【ドヤ】:簡易宿泊所(東京では簡易旅館)のこと。宿(やど)の逆読み。6〜8人で一室のベットハウス(一泊1500円前後)と3畳弱の個室(2000円超)がある。
【ドヤ保護】:生活保護で居所のない人を保護する場合、施設やアパートをすぐに確保できないなどの理由で、ドヤを居所として保護すること。
【トンコ】:自己の意志で生活保護を中断すること。病院や施設から自己退院(所)するときにも用いる。
【飯場】:建設・土木作業現場の近くに設けられた作業員の寄宿舎。最近では街の中に飯場があることが多い。ケタ落ち半場ではツケで日用品を購入できるが価格が市価より高く、食費も含めて契約期間満了時に精算するとほとんどお金が残らないことがある。
【日雇い特例健康保険】日雇い労働者対象の健康保険。
【日雇い労働者手帳(白手帳)】:職安が発行する日雇い労働者対象の雇用保険手帳のこと。就業日に印紙を貼付する。前月・前々月に26日以上の就業が認められれば、アブレ手当てが支給される。盆暮れにはモチ代・氷代という意味合いで一時金が出る。
【法外援護】:生活保護法に基づかない援護のこと。乾パンや切符を支給したり、シャワー設備を提供したりする。
【マグロ】:路上強盗のこと。「シノギ」、「モガキ」とも言う。
【寄せ場】:主に建設産業を中心とした企業が、日雇いを始めとした短期雇用労働者を雇い入れる集約的な場所であり、多数の日雇い労働者が仕事を求めて集まる場。大阪・釜ヶ崎、東京・山谷、横浜・寿、名古屋・笹島などが代表的。
【夜回り(パトロール)】:支援団体や当事者が夜間、野宿者の安否確認のために、巡回すること。同時に情報を載せたチラシを配ったり、おにぎり、ゆで卵、スープを配ることもある。
参考:第30次寿越冬闘争報告集、東京都社会福祉士会資料など
人間が心身共に健康な生活をおくるためには次の5つの条件がそろわねばならない。
(1)衣・衛生的な衣服
(2)食・栄養バランスのとれた食事
(3)住・厳しい気候をさけ健康を保つことが出来る住居
(4)安全・暴力から身を守ることが出来る環境
(5)希望・社会から疎外・排斥されず、将来に希望を持てること
これらの条件が自分自身で獲得できないという点で、野宿者問題と難民問題は同次元の問題であり、野宿者とは経済的な国内避難民と考えることができる。即ち、難民救援と野宿者支援は同じ視点に立って活動を行うことが出来るのである。国際協力に興味を持つシェアのボランティアの多くが、野宿者支援活動に協力を続けていることは以上のような理由があると考えている。難民に対しては、国連・NGOなどの国際援助機関が衣・食・住・安全を保障し、世界から注目を受けるが、野宿者にはごく小規模の支援団体が不十分な食料を提供することしかできず、その他の支援がほとんど無いのが現状である。野宿者は難民より悲惨な生活を強いられていると言えるのである。
野宿者の平均年齢は50代であり、45歳から65歳未満が大多数を占める。主に現場での肉体労働を長年続けており、経済不況の影響を最も大きき受ける人達である。また生活習慣病発症年齢層でもあり、多くが高血圧・糖尿病・胃潰瘍に罹患しているため、野宿生活自体がこれらの基礎疾患の悪化要因となっている。野宿者の平均死亡年齢は新宿や大阪での調査では50代後半であり、結核罹患率は一般住民の数十倍に達し途上国と肩を並べている。先進国であるはずの日本の都会の一角に健康指標が途上国と同じレベルの集団がおよそ2万人存在するのである。

このような野宿者の現実に対し、公衆衛生や保健行政関係者の関心が高いとは言えない、かつ福祉行政との連携もうまくとられてはいない。過去12年野宿者支援活動を行ってきた自分が、みなさんにアピールするため、ボン・パルタージュの紙面を借りて野宿問題をシリーズでお届けします。
【アオカン】:野宿の意、青空簡易宿泊所の略。明治時代の東京市の社会調査に、野宿することを「オカンする」という表記がある。青空+オカン=アオカンと思われる。
【アブレ】:失業の意。日雇い労働者が職にあぶれたときに使う。
【エサ拾い】:ゴミ箱などで残飯をあさること。
【越年越冬闘争】:年末年始期は仕事や店舗が長期間休業する。そのため、日雇い労働の賃金がなく、かつ飲食店からの残飯もなくなり、福祉事務所の対応もなくなる。野宿者にとって寒冷な気候もあり、非常に生き延びることが困難な期間である。そのため支援団体ではこの時期に合わせて、重点的に炊き出しや夜回り活動を行い、野宿者の健康維持を図っているところが多い。「闘争」は厳冬期を生き抜くための戦いの意。
【顔付け】:日雇い労働者が手配師を通さずに、直接過去に雇われた経験があるなどなじみの職場に雇われること。
【片づけ(仕事)】:建設現場での雑用や清掃などの軽作業。
【狩りこみ】:野宿者が野宿状態から半強制的に施設などに収容されること。
【ケタ落ち】:賃金・技術などの程度が低いこと。ケタ落ち職場、ケタ落ち病院など。
【シノギ】:路上強盗、マグロと同義。
【(日雇い)職安】:公共職業安定所労働課の出張所のこと。寄せ場にあり日雇い就労紹介とアブレ手当の支給が主な業務である。
【炊き出し】:民間の野宿者支援団体、宗教団体(キリスト教関係団体が多い)による、定期的な食糧配給。おにぎり、カレー、どんぶりなど様々だが、圧倒的に炭水化物が多く、野菜は少ない。山谷では諸団体が行っておりほぼ毎日あるが、新宿では全部あわせても週3回程度。配給に余裕があるときはお代わりなど食いだめをすることがある。
【ダンボール村】:1994年から1998年にかけて都庁への地下通路から新宿西口地下広場に集中したダンボール製の小屋群。多いときには200軒を超えた。
【チケット並び】:コンサートや野球などの前売り券を買う仕事。
【手配師】:労働者に仕事を紹介(「手配」)し、業者から紹介手数料を得ることを生業とする者。暴力団関係者もおり、寄せ場・駅・公園などで労働者に声をかけるが、低賃金など悪条件のところが少なくない。
【当事者】:野宿当事者。支援者と対比する意味
【特診券】:特別診療券。社会福祉法人の病院では、生活困窮者に対し無料・低額診療を行っている。福祉事務所がその券を預かり、来所者の中で簡単な治療を希望する人、生活保護を必要とするかどうかの鑑別診断などの目的で交付している。
【ドヤ】:簡易宿泊所(東京では簡易旅館)のこと。宿(やど)の逆読み。6〜8人で一室のベットハウス(一泊1500円前後)と3畳弱の個室(2000円超)がある。
【ドヤ保護】:生活保護で居所のない人を保護する場合、施設やアパートをすぐに確保できないなどの理由で、ドヤを居所として保護すること。
【トンコ】:自己の意志で生活保護を中断すること。病院や施設から自己退院(所)するときにも用いる。
【飯場】:建設・土木作業現場の近くに設けられた作業員の寄宿舎。最近では街の中に飯場があることが多い。ケタ落ち半場ではツケで日用品を購入できるが価格が市価より高く、食費も含めて契約期間満了時に精算するとほとんどお金が残らないことがある。
【日雇い特例健康保険】日雇い労働者対象の健康保険。
【日雇い労働者手帳(白手帳)】:職安が発行する日雇い労働者対象の雇用保険手帳のこと。就業日に印紙を貼付する。前月・前々月に26日以上の就業が認められれば、アブレ手当てが支給される。盆暮れにはモチ代・氷代という意味合いで一時金が出る。
【法外援護】:生活保護法に基づかない援護のこと。乾パンや切符を支給したり、シャワー設備を提供したりする。
【マグロ】:路上強盗のこと。「シノギ」、「モガキ」とも言う。
【寄せ場】:主に建設産業を中心とした企業が、日雇いを始めとした短期雇用労働者を雇い入れる集約的な場所であり、多数の日雇い労働者が仕事を求めて集まる場。大阪・釜ヶ崎、東京・山谷、横浜・寿、名古屋・笹島などが代表的。
【夜回り(パトロール)】:支援団体や当事者が夜間、野宿者の安否確認のために、巡回すること。同時に情報を載せたチラシを配ったり、おにぎり、ゆで卵、スープを配ることもある。
参考:第30次寿越冬闘争報告集、東京都社会福祉士会資料など
文責:大脇甲哉
機関誌「Bon Partage」No. 128(2006年3月)掲載
機関誌「Bon Partage」No. 128(2006年3月)掲載