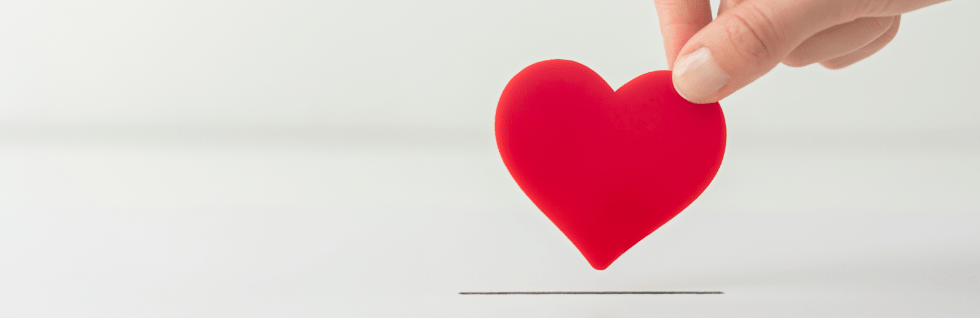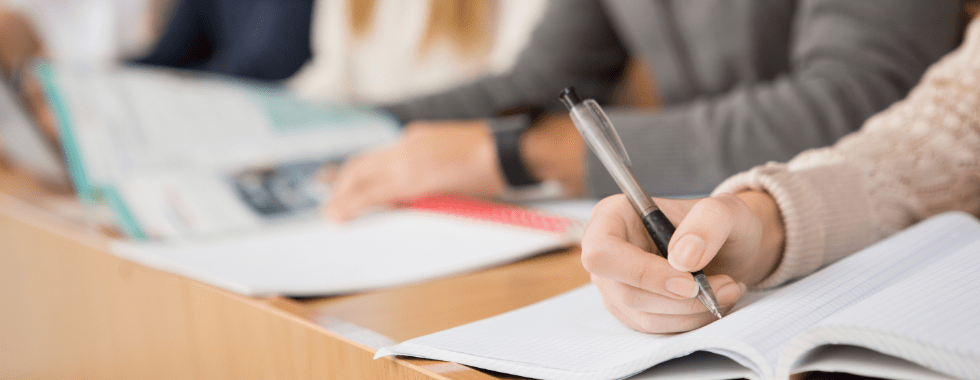シェア=国際保健協力市民の会とは
1983年から国際保健活動に
取り組む国際協力NGO
VISION
理念
Health for All!
すべての人々が健康に暮らせる世界の
実現を目指します。
MISSION
使命
困難な状況にある人々が、自ら健康を改善することを支援します。
格差や不公正の解消のため、共に考え行動し、世界に働きかけていきます。
シェアの活動の特長

現場実践主義
現場に保健医療や開発分野の日本人専門家を派遣し、現地住民と共に活動に取り組みます。シェアの活動は、地元の人の主体性を尊重したうえで実施されます。

地道で継続的な長期間の活動
基本的な保健医療サービスが途上国で行われ、それが現地の人々によって維持改善されるように、長期間関わることを原則としています。緊急支援の際も同様です。

国内活動も重視
途上国の現場で国際保健活動を行う一方、在日外国人への医療支援・途上国における活動や起きている課題を市民へ伝える啓発活動等、日本での活動も精力的に実施。
数字でみるシェア
シェア活動地の保健医療の現状
<出典>
※1,2,3,4 世界子供白書2023(UNICEF)
※5 Adolescentpregnancy situation in South-East Asia Region(WHO,2021)
シェアの活動の成果

国際保健支援活動を
重ねてきた年数
40年
- カンボジア
34年 - タイ
25年 - 日本
32年 - 東ティモール
24年