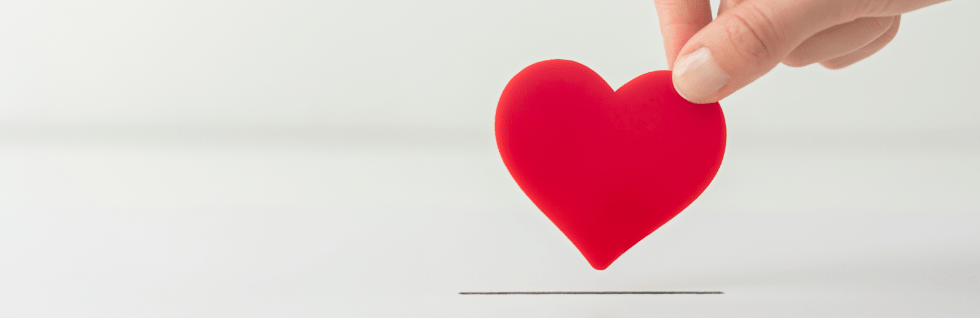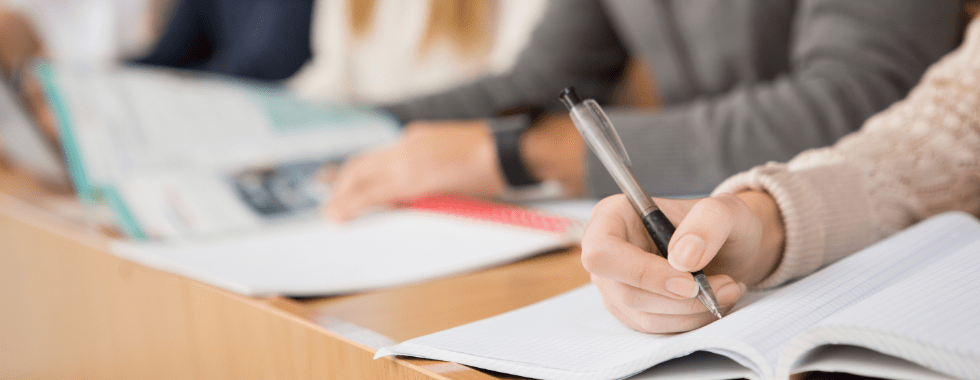野宿者
野宿者
1990年代後半経済不況に伴い、一般の会社員や住み込み勤務の人々が、リストラによる生活破綻や希薄な家族関係により、いきなり野宿生活者になるというケースが頻繁に見られるようになり、急激に増加した野宿者が社会問題となった。野宿=住所不定となることは、地域住民でなくなることを意味し、さまざまな行政サービスや社会保障を受けられなくなる。例えばアパートの家賃を払えなくなり野宿生活になったとたんに、居所不明で生活保護を受けられなくなるという事態におちいるのである。
人間が心身共に健康な生活をおくるためには次の5つの条件がそろわねばならない。
(1)衣・衛生的な衣服
(2)食・栄養バランスのとれた食事
(3)住・厳しい気候をさけ健康を保つことが出来る住居
(4)安全・暴力から身を守ることが出来る環境
(5)希望・社会から疎外・排斥されず、将来に希望を持てること
これらの条件が自分自身で獲得できないという点で、野宿者問題と難民問題は同次元の問題であり、野宿者とは経済的な国内避難民と考えることができる。即ち、難民救援と野宿者支援は同じ視点に立って活動を行うことが出来るのである。国際協力に興味を持つシェアのボランティアの多くが、野宿者支援活動に協力を続けていることは以上のような理由があると考えている。難民に対しては、国連・NGOなどの国際援助機関が衣・食・住・安全を保障し、世界から注目を受けるが、野宿者にはごく小規模の支援団体が不十分な食料を提供することしかできず、その他の支援がほとんど無いのが現状である。野宿者は難民より悲惨な生活を強いられていると言えるのである。
野宿者の平均年齢は50代であり、45歳から65歳未満が大多数を占める。主に現場での肉体労働を長年続けており、経済不況の影響を最も大きき受ける人達である。また生活習慣病発症年齢層でもあり、多くが高血圧・糖尿病・胃潰瘍に罹患しているため、野宿生活自体がこれらの基礎疾患の悪化要因となっている。野宿者の平均死亡年齢は新宿や大阪での調査では50代後半であり、結核罹患率は一般住民の数十倍に達し途上国と肩を並べている。先進国であるはずの日本の都会の一角に健康指標が途上国と同じレベルの集団がおよそ2万人存在するのである。
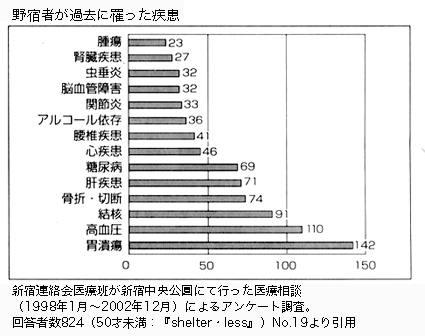
東京および新宿の野宿者の特徴
東京の特徴
東京都23区内の野宿者数は2005年8月時点で4263人である。東京都による概数調査は1995年以降継続して行われている。1995年には3300人であり、1997年(3700人)まで漸増傾向を示した。その後急激に増加し1999年に最大(5800人)となって以来漸減しつつ現在に至っている。
東京の野宿者の特徴は、6割以上が50歳から64歳の男性で、多くは現在単身で家族との連絡が途絶している。東京出身者は2割弱だが、それ以外の人の7割が20歳代までに上京し、その年代は東京オリンピックをはさんだ高度成長期が多い。常勤社員から日雇い労働者を経て野宿に至るケースが多い。寄せ場経験のない人も多いなどである。
東京都の野宿者対策は、1960年頃山谷地域(*)で連続して発生した暴動が契機になり、国・都が山谷対策として1962年に東京都山谷福祉センターを開設し、日雇い労働者の生活相談・労働相談を行った。現在は財団法人城北労働・福祉センターへ引き継がれている。1990年代後半の野宿者の急増に対し、東京都は新たな野宿者対策として2001年3月野宿者の自立支援システムを発表した。すなわち緊急一時保護センター、自立支援センターを経曲することにより生活の自立を目指すシステムである。現在では5か所の緊急一時保護センターと5か所の白立支援センターが設置されている。また2004年9月から低額家賃の住居を提供し、かつ臨時就労の形で入居後半年間仕事を提供することにより、野宿生活からの脱却をはかる地域生活移行支援事業が始まった。5つの公園から合計888名(2005年10末現在)が野宿からアパート生活に移行した。この事業により23区内の野宿者数は2004年8月の5497人から2005年8月の4263人へと1200人以上減少した。
(*)台東区及び荒川区の日雇い労働者が多くいる地域の名称。
新宿の特徴
新宿区には2006年3月現在約500人の野宿者が生活していると考えられる。集住地域は新宿中央公園、戸山公園、新宿駅周辺である。
1996年1月以前にはJR新宿駅西口から都庁に通じる地下通路に集住し、その数はおよそ200人、新宿駅地下・地上をあわせて640人であった。
1996年には西口地下ロータリー周囲に移動し、地下には450人、全体では610人が新宿駅周辺に生活していた。1998年2月西口地下ロータリー南側のダンボール村の火災事故の後、都庁西隣の新宿中央公園に集住するようになった。1999〜2000年越年期には平均680人が新宿駅・新宿中央公園を中心に一時的に夜を過ごし、常時約200人が新宿中央公園で生活していた。また戸山公園にもおよそ200人の定住野宿者がいた。その後はほぼ同じ規模で推移し、2004年8月の東京都による概数調査では新宿区内の野宿者数は1102人であった。この調査は夜間のみ新宿駅などで寝て日中は仕事や公共施設で過ごす人たちはカウントされておらず、実際にはおよそ2?3割増の野宿者がいたと考えられる。
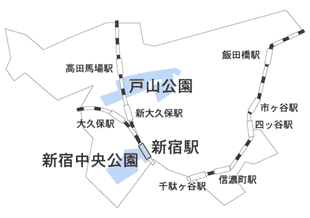
2004年9月から2005年2月までに地域生活移行支援事業により、新宿中央公園および戸山公園の野宿者417名が民問アパートや都営住宅に移り住んだため、新宿区の野宿者数は減少傾向にあり、2005年8月の概数調査では新宿区内の野宿者数は463人である。新宿連絡会による新宿中央公園の炊き出し実数は、地域生活移行支援事業施行以前には約700人であったが、2006年3月現在では約300人程である。
新宿など23区西部に生活する野宿者の特徴は、平均年齢が53歳くらいで全国平均より2歳以上若く、野宿生活の期問が短く、移動型の寝場所が多い、直前職ではサービス業に従事していた人の割合が高く、寄せ場経験のない人が多いなどである。現在従事している仕事では建設(日雇い)に従事する人が最も多く、本集め・チケット並びなどの都市雑業に従事している人が多い。
文責: 新宿連絡会医療班 大脇甲哉
機関誌「Bon Partage」No.129(2006年5月)掲載
野宿者の健康問題(新宿連絡会医療班の路上健康相談)
新宿連絡会は1994以前から活動を行っており、野宿者同士の自主的な互助組織をサポートする形で、通年活動としてパトロール・救急対応、越年期活動として簡易シェルターを設置し衰弱者の介護を行ってきた。この活動に医療関係者が次第にボランティアとして参加するようになり、新宿連絡会医療班が1996年3月に発足した。1998年1月までは、ダンボール村のあった新宿西口ロータリー横の地下通路において、連絡会の炊き出しと同時に机を出して、医療者による健康相談を毎月1回第2日曜日に行い血圧測定・市販薬提供を行った。1998年2月ダンボール村の火災事故により医療相談は一時中断したが、野宿者が移住した新宿中央公園で連絡会の定期炊き出しが開始された1998年4月から医療班も活動を再開した。その後現在まで毎月第2日曜日の医療相談活動を継続している。その後、現在まで毎月第2日曜日の医療相談活動を継続している。越年期には集中支援活動として医療テントを設置して24時間の相談・介護体制を組んでいる。
1996年4月から2006年3月までの10年間に、定期医療相談と越年期医療相談で医師が相談記録を作成した受診者は、延べ3840人であり、複数回受診した人を除いた受診者実数は3142人であった。延べ受診者の内2886人が定期医療相談を、954人が越年期医療相談を受診した。受診者の平均年齢は53.2歳、最も若い受診者は20歳、最も高齢の受診者は84歳、女性の割合は3.5%であった。また医療相談受診者の内1095人が医療機関を受診し、そのうち152人が入院治療を行った。
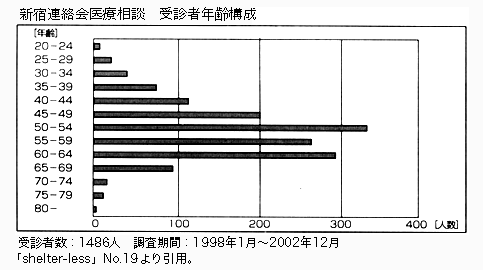
2000年度から受診者の増加に対応するため、すべての受診者の相談を医師が行い記録を残す従来の方式から、血圧計測のみの相談者は別記録とし、症状が軽度で風邪薬や湿布・軟膏類で対応できる受診者には看護師が口頭で問診を行い市販薬を提供し、重症者を医師が相談するシステムに変更した。血圧計測のみは平均40人程、薬の提供のみは70から110人程である。そのため1999年度に比べ2000年以降は総受診者数が90人程、受診者実数が30人程減少した。しかし医療機関を受診した人数の減少は見られず、重症例に集中して医師の相談を行う方式に変更した効果が見られた。
地域生活移行支援事業開始後、2004年12月以降の医療相談受診者数が減少傾向にある。新宿区では2004年9月から2005年2月の間に421人が野宿生活からアパートに移行した。2003年度の相談者数及び医療機関受診者数はそれぞれ474人と117人であるが、2005年度には252人と82人に減少している。
受診者の年齢層は45歳から64歳の層が73%を占める。1996年から2005年まで受診者の平均年齢は53歳前後でほぼ一定している。医療機関受診時の疾患は、高血圧・胃潰瘍・腰痛・結核・湿疹・打撲・糖尿病など、循環器・運動器・消化器・皮膚・呼吸器疾患の順に多かった。また既往歴は、胃潰瘍、高血圧、結核、骨折、糖尿病、脳血管障害など、消化器、循環器、呼吸器、運動器、肝胆道系疾患が多かった。
野宿者の平均死亡年齢が50歳代であり、結核罹患率も一般人口の100倍に達すると考えられる。野宿者の健康状態は、最貧途上国と同じレベルであると言える。野宿者の死亡原因は大阪市監察医事務所死体検案・解剖結果によると、心筋梗塞などの心疾患、肝炎・肝硬変、肺炎、結核、脳血管障害、胃潰瘍などの疾患と、凍死、栄養失調・餓死が主なものである。新宿連絡会・医療班健康相談における既往歴と死体検案による死亡原因疾患はほぼ一致する。
野宿者の健康を改善するために最も必要なものは、医療ではなく衣食住の環境を整えることである。生活保護を中心とした社会保障と就労支援による生活の自立が最も重要な課題である。野宿者の健康にとって医療相談活動は、路上死に至らないようにするための最終的な支援であると考える。
文責:新宿連絡会医療班 大脇甲哉
機関誌「Bon Partage」No.130(2006年7月)掲載
特定非営利活動法人訪問看護ステーションコスモス
立ち上げ
訪問看護ステーションコスモスは7年前に看護師だけで立ち上げたステーションです。山谷地域を含む訪問看護ステーションとして、NPO(特定非営利活動)の法人格を取得し、看護師3名事務職員1名から出発しました。多くの人達に支えられ、現在では看護師20名が集まるステーションに成長しました。当初は山谷地域を含めた訪問看護、健康相談を行い、その後横浜寿地域の訪問看護、山谷地域のデイサービスと事業を進めてきました。コスモスで働く看護師は海外で難民の支援を行ったり、路上生活者の支援を行ったりしてきた看護師も多く、他の訪問看護ステーションとは一味違うステーションに成長しました。皆勉強熱心で心優しい看護師達の集まりです。ターミナルグループ、褥創グループ、健康相談グループ、精神グループに別れ、それぞれ自主的に勉強会を行い、昨年は褥創学会、公衆衛生学会、結核病学会でも事例報告をしました。
看取り
山谷地域、横浜寿地域は工事現場や港湾現場等で働く日雇い労働者が多く集まり、労働者はドヤと呼ばれる簡易旅館で寝起きをしています。しかしバブル経済崩壊以降は仕事がなくなり、その日暮らしの労働者はホームレス生活を余儀なくさせられることも多く、山谷・寿地域は日本の中で最も貧しい地域の一つとなりました。そこに住む人達は親兄弟とは縁を切った単身者が多く、昔元気で働いていた人達も高齢化し多くは病気を持つようになりました。
山谷地域では他の支援団体と協力し、単身で生活をしている人達の看取りも行います。その時その時の出会いを大切にし、可能な限り、そして荼毘にふし骨を拾うまで付き合うこともあります。どのような境遇に生活する人達にも差別することなく関わることはコスモスの設立理念にもなっています。勿論、単身の人達ばかりでなく家族と一緒に生活する人達、小児の重症心身障害児等も訪問し、看護を提供しています。今では地域にしっかり根を張り、無くてはならない頼られる存在にもなっています。
健康支援
コスモスでは、訪問看護だけではなく路上の人達への健康支援も行っています。デイサービスの場所を利用し、第1・3土曜日には健康相談・入浴サービス・喫茶サービスを実施しています。また、山谷地域の夏祭り、越年での健康相談、散髪、路上生活者が集まる城北労働・福祉センター娯楽室での健康相談、簡易旅館の巡回相談も行っています。健康相談を実施する中で結核発病者の発見にも努めています。
想い
コスモス事務所のシャッターが閉まると多くの人達がダンボールを運び野宿をします。冬の厳しい寒さは野宿者の命を奪うことも多く、何度か救急車の要請をしたこともあります。残念ながら息絶えていた人もありました。このような光景は忘れてはいけない、慣れてはいけない山谷の光景と思っています。路上死や旅館での孤独死の人達を一人でもなくす為に・・・、コスモスがその名のように可憐な花を、献身的にそして根強く、ほんの一輪でも咲かせることが出来たら・・・と思い日々看護に取り組んでいます。
訪問看護ステーションコスモス
住所:〒111-0021 東京都台東区日本堤1-12-6
E-mail:s.cosmos@cronos.ocn.ne.jp
訪問看護・居宅介護支援
TEL:03-3871-7228 FAX:03-3871-7229
デイサービス(デイサービスセンター コスモス)
TEL/FAX:03-3871-7513
訪問看護ステーションコスモス 山下眞実子
機関誌「Bon Partage」No.131(2006年9月)掲載
Donation すべての人と健康を
シェアする活動を、
毎月の寄付で
応援しませんか?
シェアは、いのちを守る人を育てる活動として、保健医療支援活動を現在
東ティモール・カンボジア・日本の3カ国で展開しています。
- 寄付で応援する(support/donation/index.html)
寄付で応援する
マンスリーサポーター、
一回のみの寄付、
遺贈による寄付などが可能です。 - モノを集めて、 モノを購入して支援(support/mono.html)
物の寄付で応援する
書き損じハガキ、未使用の
はがきや切手、商品券、使用済みの
切手による寄付が可能です。 - ボランティア・インターンとして参加(support/volunteer/index.html)
参加して応援する
スタッフ、ボランティア・
インターンとしてシェアに
参加することが可能です。