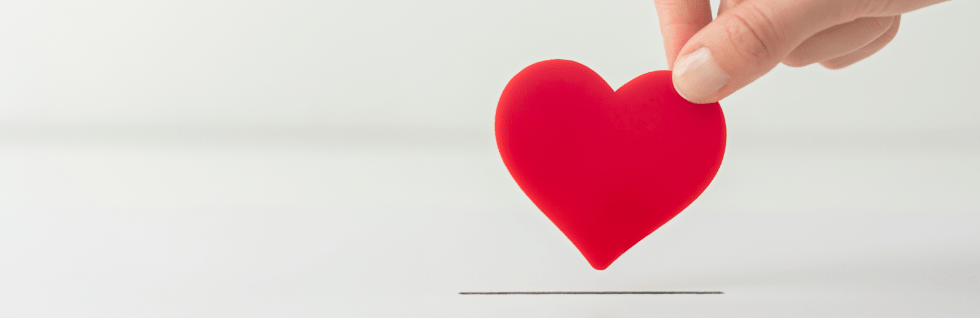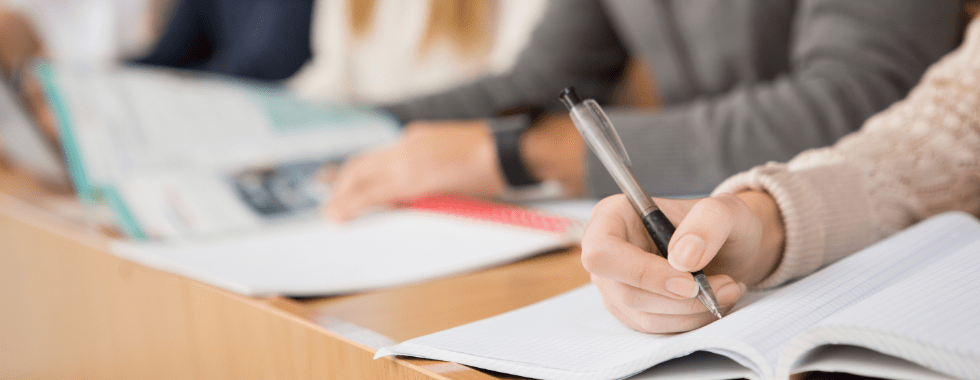在日外国人の健康

在日外国人の健康 No.1
世界経済のグローバル化によって、多くの人々が働く場を求めて国境を越えていくようになった。しかし、移住先で医療や福祉の支援を受けることができなければ、いざ健康を害したときの問題は深刻になりがちである。1990年ごろより急速に社会問題となった外国人医療の問題について、今回は日本での背景について解説する。
在日外国人とは
2007年5月法務省入管局の発表によれば、日本に滞在し外国人登録をしている人の数は208万人であり、人口の1.6%を越えている。一方、在留資格がなく滞在している超過滞在者の人数は、最盛期約30万人であったが、現在15万人を切り半減している。
国籍別では、韓国(1位)、中国(2位)、フィリピン(4位)といった極東・太平洋地域の出身者が3分の2を占める。また、ブラジル(3位)、ペルー(5位)など南米出身の日系人も2割程度を占めている。韓国・朝鮮・中国出身で1950年以前より滞在する特別永住者とその子孫の占める割合は大きく減少し、1990年以降に来日したいわゆるニューカマー外国人の割合が多い。
外国人労働力と日本経済
1990年前後、日本がバブル経済ににぎわっていた頃、多くのアジアの国ではちょうど外国企業の進出で農村と都市の格差が大きくなってきた時期であった。こうした中で人手不足の深刻な日本に多くの外国人労働者が訪れ多くの中小企業が雇用するようになった。しかし、単純労働に従事する労働者の受け入れを認めない入国管理政策の下では法律に違反した雇用となり、社会保障の外に置かれ強制退去を恐れて就労することとなった。こうした労働者の中には違法な就労であることを納得づくで来日した人々もいれば、雇用契約ができれば就労資格が得られると思ってきたもの、留学で来て資格が切れたものなど多様であった。
日系人の増加
在留資格をなくして働く外国人労働者が多数いるという実態と、単純労働を受け入れないという行政上の方針との乖離が進み、政府は労働力不足を超過滞在外国人に頼らずに補う方法を模索するようになった。こうして1990年に日系人であれば自由に就労ができるよう入管法が改定された。こののちブラジル、ペルーなどからの日系人労働者が急増することとなった。
しかし、その後の景気の減速とあいまって1992年をピークに超過滞在外国人の数は減少を始める。超過滞在外国人の多くが個人で工場や建設現場などに雇用されていたのに対して、日系人の多くは人材派遣会社を通じて集団で企業に派遣され就労する場合が多い。このため在留資格はあっても言葉が不自由な人々が少なくない。
その後、農業・漁業・家内工業などの業界団体が組合を作って研修生を受け入れることが許可され、2000年ごろからは研修生という形で実質的な就労する人の数が急増している。研修生は医療保険が提供されているが、労働者として認められず8万円にも満たない低賃金で実質的な労働を担わされていることに対する問題が指摘されている。
外国人医療問題のはじまり
実は、1990年までは、在留資格のない外国人であっても重篤な病気で緊急医療を要した場合に行政が生活保護法を援用して医療費を捻出することが可能であった。しかし、1990年10月に当時の厚生省が口頭の通達で在留資格のない外国人を生活保護の対象から除外するよう指導を行った。これによって在留資格のない外国人の場合、緊急医療が必要でも医療費が医療機関に払われないという事態が起こるようになった。国民皆保険が整って以来、全ての人に等しく治療を提供していた日本の医療に、この時大きなほころびが生まれたのである。
文責:シェア副代表理事 沢田貴志
機関誌「Bon Partage」No.140(2008年7月)掲載
在日外国人の健康 No.2
現在日本に在住する外国人の数は200万人を超え更に年々増加を続けている。経済がグローバル化する中で人の移動が活発になったことの当然の結果である。日本で働く外国人は一時的な出稼ぎという目で見られることが多いが、出生率の低下の中で貴重な労働力として日本の経済を支える人材であり、今後日本の社会に移民として円滑に定住できるようにすることが既存の日本社会の構成員にとっても重要となってきている。日本で生活する外国人は、いざ病気になった時様々な壁にぶつかる可能性がある。こうした問題を自己責任に帰するのではなく、日本の社会が解決できるよう体制を整えることが必要である。
言葉の障壁
海外で生まれて日本語を母語として育っていない外国人にとって日本で医療を受ける最大の障壁は言葉の壁である。日本では病院が医療通訳を配置していることは極めてまれであり、医療従事者も英語以外の言語に対応できることは非常に少ない。しかし在日外国人の母語としてニーズが高い言語は、中国語・韓国朝鮮語・ポルトガル語・スペイン語といった言語である。
医療現場での通訳利用
こうした言語への対応は日系ブラジル人が多い一部の地域の病院などを除いてはほとんど行われていない。北米・北西欧州・豪州などに比して日本の医療通訳体制の整備は遅れているが、神奈川県・京都市など地方自治体の中にも医療通訳の育成と派遣を行う取り組みが始まって来た。言葉がわからなければ受診が遅れたり診断が円滑につかずに高額の医療費を要する事態となることもある。また、せっかく診断がついても説明が十分伝わらず有効な治療に結びつかないことも予測される。通訳体制の整備は外国人医療の向上のために必要な重要な課題である。
医療費問題と健康保険
日本は国民皆保険制度となっており、健康保険に加入していれば自己負担は3割であり、月あたり約7万円を超えた高額医療費は後から給付され理屈の上では医療費を理由に医療が受けられないことは起きにくくなっている。しかし、1990年代から、国民健康保険加入の条件に1年以上の在留資格をあげる施策が行われて以来、短期滞在者・超過滞在者は国民健康保険への加入が事実上できなくなった。超過滞在外国人の数は現在半減しているが、商用や家族滞在などの数は増えており常時数10万人の健康保険を持たない外国人が日本に在住している。
日系人と健康保険
1990年以降急速に増加した日系人は人材派遣会社に所属し工場等に派遣されていることが多い。しかし、少なからぬ人材派遣会社が社会保険への加入を行っておらず、多くの日系人労働者が1年以上の在留資格を持ちながら無保険になっていた。現在は、派遣会社にたいして健康保険への加入を促す指導が行われている。
感染症と外国人医療
実感染症予防法では、隔離を要する1類・2類の感染症については隔離が必要な期間の公費での医療を定めている。また、結核については外来治療についても患者負担を軽減する制度を設けている。生活基盤の安定していない外国人は、結核・HIVといった感染症の影響を受けやすく、これらの制度を円滑に活用して医療へのアクセスを確保することが重要である。
未払い補填事業
開発途上国出身の外国人を雇用する工場や建設業者が急増し、健康保険に加入できない外国人の数が急増したのが1990年代初頭である。このころ医療費の未払いに対する懸念から診療拒否事件が頻発し、社会問題となった。生命に危険がある病人を医療費が支払える確証がないというだけの理由で治療しないことは、医師法に反する行為である。そこで東京・神奈川・群馬などの主として関東地方の自治体が外国人救急医療費の未払いを補てんする事業を開始し、医療機関の損失を埋めることで混乱を防止する対策を行っている。しかし、自治体によって予算額が大きく異なっており、実質的に制度が機能している自治体は極めて少数である。近年の病院経営の悪化を背景に診療拒否が増加している兆候があり、国レベルの対策が必要だとの指摘もある。
文責:シェア副代表理事 沢田貴志
機関誌「Bon Partage」No.141(2008年10月)掲載
在日外国人の健康 No.3
日本に在留する外国人は200万人を超えたが、その多くは若い働き盛りの人々である。日本の経済を支える彼らの健康を守れるかどうか日本の地域社会の在り方が問われている。事例を交え、課題と取り組みについて解説する。
増加を続ける外国人への診療拒否
外国人人口が急増した1990年代、外国人への医療も幾つかの改善が見られた。しかし、この数年間病院経営の悪化が進む中で外国人医療をめぐる環境はむしろ悪化しているように見受けられる。昨年シェアが毎日新聞の取材を受けた際に、医療費の支払いが理由で治療が受けられず生命の危険にさらされた外国人の事例をまとめてみた。この結果、私たちが把握しただけで2006年には5件、2007年には7件の医療費を理由とした診療忌避が認められ、経済的な理由で治療が受けられず死亡したと考えられる外国人が3人いた。現実にはこの数倍の診療忌避が生じていると予測される。医師法は「正当な事由なく診療を拒んではならない」と定めており、医療費の支払いが不確かであるというだけで治療を提供しないのは医師法違反に問われる問題である。生命に危険が及んでいる状態であればなおさらである。
海外からの問題提起
2008年7月タイのエイズ患者らで作るTNP+(タイHIV陽性者ネットワーク)が日本政府と長野・茨城県両県知事あてに要望書を提出した。日本でエイズを発病した2人のタイ人が脳の合併症で意識障害や麻痺を生じながら経済的な理由やビザが切れていることで緊急医療をなかなか受けられず死亡したり障害を残したりしたためである。報道によれば、この事件を受けて長野県は医療通訳の制度化を行うとのことである。まずは長野県の英断を評価するべきであろう。しかし、こうした事態が繰り返される背景には、赤字を増やす患者を受け入れたくないという意識が医療経営者の間に広がり、有形無形の形で医師にその圧力が加わっているからである。通訳制度を導入しても、医療機関が健康保険のない外国人を避けようとする現実が変わらなければ制度は使われないだろう。
自治体の対策
こうした中で、東京都・神奈川県では深刻な診療忌避が少ない。この背景には行旅病人法・未払い補填事業という2つの制度に必要な予算が割り当てられていることがある。これらの制度は、外国人の病人に必要な治療を提供した医療機関に対して、一定の条件下でその損失の一部を自治体が補てんするものである。これによって医療機関の診療忌避が減っており、早期の治療開始が促進するため重症患者が減少する。現実に、神奈川県では平成18年度の予算が年間2000万円であったのに対して利用が1380万円にすぎず、外国人未払い医療費に減少傾向すらみえる。特筆すべきことは、この両県が外国人人口当たりのエイズ発症数が関東甲信地域で最も少なく、結核発生も減少傾向がみられることである。
検診や言葉の支援
こうした改善と両自治体が外国人のための検診、通訳制度、未払い医療費の補填といった積極的な政策を展開していることとは無関係ではないだろう。早期発見や受診の機会を提供し、診療拒否が起きにくいsafety-net(安全網・安全策)を作ることは医療経済上も効果的なのだ。一方こうした制度がない自治体では、医療費が回収できないことや言葉のトラブルを恐れる病院が診療を婉曲に拒みがちである。この結果、治療を受けられないままに病状を悪化させていく外国人の例が目立つ。母国に帰るためには航空機を使わざるを得ない以上、病状を一定回復させなければ帰国はできない。結局どこかの病院が最後に引き受けて、より時間と費用をかけて治療をすることになる。その病院の多くが公立病院であるならばこれは税金の大きな無駄遣いである。
国際社会の信頼を得るために
過去10年で健康は人権であるという意識が開発途上国にも広がってきている。こうした中で医療費が払えそうもないからと治療が遅れ、死亡したり障害を負う病人が続けば国際的な非難を浴びるだろう。そもそも、健康保険のない外国人には3カ月ビザの商人、日本人に嫁いだ娘の子育て支援に来た母親、大使館で雇用される運転手など多様な人が含まれている。こうした人々の急病への備えも必要である。東京・神奈川の実践に習い外国人のための健診・通訳制度・未払い補填制度のなど効率的で人道的な医療体制の整備が急務である。
文責:シェア副代表理事 沢田貴志
機関誌「Bon Partage」No.142(2009年1月)掲載
在日外国人の母子保健制度適用ガイドライン
すべての女性はリプロダクティブ・ヘルス/ライツの理念のもと、安全に妊娠・出産することができ、健康に子どもを育てることができるための適切なヘルスケア・サービスを受ける権利を有している。しかし、はたしてその「人権」は、在日外国人母子にも保障されているであろうか。在日外国人の人権保障、法的保護は甚だ遅れている。ましてやオーバーステイ状態にある人々は、人として無権利状態に置かれていると言っても過言ではない。特に、母子保健上の問題は妊娠、出産、育児のそれぞれの過程で深刻であり、無視できない状況となっている。オーバーステイの母親から生まれた子どもたちの成育権は、「入国管理法違反」であるという理由から、法の外に放置されている。母親は発覚することを恐れ、公的な場所にはほとんど訪れない。一方、現場では保健医療担当者の無知や偏見による「独断」がまかり通り、まるで「在留資格の有無」によってすべての「母子保健」が決まるようである。母親は、妊婦健診を受けられず、ハイリスク状態で分娩に臨むことになる。出生証明書はどこにも提出されず、子どもは無国籍状態になり、予防接種も受けられず、病気や怪我をしても病院に行くこともできずにいる。子どもが成長するにつれ、その人権侵害は深刻化し、その生活・教育環境が蝕まれていく、そして次世代連鎖をも起こしている。この悲惨な母子の状態を我々はどのように改善していくべきなのか、何ができるのか、最低限保健医療従事者が知っておくべき母子保健ガイドラインを作成した。
母子健康手帳について
母子健康手帳取得にあたって、まず必要なのは妊婦の氏名、現住所である。住所が実在するかどうかは、郵便物等で確認することができる。外国人登録証がないことを理由に、一律に母子健康手帳の交付を拒むことは適切ではない。
母子健康手帳を給付するにあたり、妊産婦の妊娠週数が進んでおり、かつ医療機関にかかっていない場合は、自己申告による妊娠届であっても受理する。母子保健サービスを一刻も早く受けられるように、配慮することが最優先である。
母子健康手帳の妊婦健診無料券あるいは補助券、乳児健診券、予防接種券などは例え別冊であろうと、本冊と一体となっているものである。母子保健法は、国籍や在留資格に関係なく、現在日本で妊娠しているすべての女性に適用されるものである。対象妊産婦の在留資格状態によって、母子健康手帳の一部を除去、破棄してはならない。
助産施設
保健医療関係者、医療ソーシャルワーカー等は、自治体との連携を密にし、当該外国人妊産婦が安心して助産施設での出産ができるよう配慮する。
公立の助産施設でありながら、出産予定日が迫っていると受け入れを拒む事象が起きているが、本来は道義上、緊急事態にある妊産婦であれば、率先して引き受けるべきである。福祉事務所の照会がない等の制度上の問題はまず、人道上の対応を行った後に、適切な措置を講じる。
入院助産
入院助産申請は、妊産婦の国籍や在留資格に関わらず入院助産申請が可能である。
収入証明のための課税証明書、あるいは非課税証明書が取れない場合は、本人の収入申告書で代用するなど柔軟な対応をする必要がある。
養育医療・育成医療
該当する医療機関の医療ソーシャルワーカー、および保健所の担当者は、該当する外国籍の子どもにとどこおりなく養育医療・育成医療制度が適用されるよう配慮する。
出生届
外国人の父母が、日本で出生届をおこなう際には、母子健康手帳などの記載をもとに、出生届の記載にミスがないよう配慮する。
出生届は、その後の子どもの在留資格、国籍取得等、人生に多大な影響を与えることを自覚し慎重に対応する。
いかなる場合にも、出産に立ち会った医師・助産師が子どもの出生証明発行を拒否することはゆるされない。
予防接種
在留資格がない子どもであっても、予防接種を受けることができる。居住地管轄内で、サービスが受けられるよう、保健所等では関係者に対し周知徹底をはかる。
文責:長崎県立大学大学院人間健康科学研究科 教授 李節子
機関誌「Bon Partage」No.143(2009年3月)掲載
DVと在日外国人
DVとは
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律H13制定、H19改正(*1))において、DVとはパートナーからの暴力は犯罪であり人権侵害であると定められた。対象は現在法的婚姻関係にあるパートナーだけではなく離婚後や事実婚にも適用され、暴力の形態も身体、精神、性的なものと広範囲である。残念ながら日本には男女間の社会的、経済的格差が存在し、双方の力関係がDVを生む温床になりうるというのが大切な視点である。
国際結婚とDV
在日外国人のDVは、婚姻などで日本へ定住する外国人女性が、夫の母国において言葉を含め文化的、経済的、社会的な力関係でも弱い立場におかれ、法律的に夫に付随する「在留資格(いわゆるビザ)」において日本人女性よりもさらに弱者となる傾向が見られる。それが外国人女性へのDVの特徴である。華やかな国際化の影には、結婚紹介(アジア、ロシア、東欧、中国の日本人孤児関係者)や、母国(アジア、中南米)からブローカーに騙され日本で働かされていたいわゆる「人身売買(取引)」の元被害者が日本人男性と国内で出会って婚姻したケースなどの、国家間の歴史、経済格差、家族関係など来日の背景に複雑な事情も潜んでいる。
外国人と在留資格(ビザ)
外国人が日本に合法滞在するには、法的婚姻とは別に日本で生活するための「日本人配偶者」という在留資格が必要であり、在留期限は最初1年間を2回更新、安定した夫婦には更に3年間、その後5年目になってやっと「永住者」の在留資格を取得できる。永住者になれば離婚しても日本に住み続けられる。もしそれ以前に離婚し「日本国籍の子の親権者」なら「定住者」に在留資格変更をする。しかし「日本国籍の子」がいない、または親権者でない場合には在留資格を喪失する。そこで、外国人女性は在留資格更新には夫の協力が不可欠、子どもと引き離されるという恐怖から、DVを耐え忍ぶという悲劇も生まれる。
配偶者暴力相談支援センター、女性(婦人)相談所、シェルター
DV法により各自治体でDV相談窓口=配偶者暴力相談支援センターが定められ、国籍や在留資格に関係なく相談をうけ、必要に応じて公立、民間のシェルターで緊急一時保護を行う。頼る家族や友人がなく福祉の情報の入りにくい外国人にとって相談窓口を知ることは、身体に危険が及ぶか否かによらず、被害を防止または最小限にとどめる点で重要である。もしDVの疑いや家族関係について悩む様子に気づいたら、被害者本人に「DVは自分が悪いのではない、暴力は犯罪であり、相談する場所がある」ことを知らせる必要がある。夫やその関係者が同行する場合、彼らが同席していない場面を見つけ、被害者の母国語のDVに関するパンフレットや相談電話番号(内閣府や各自治体作成(*2))を渡すことは支援の糸口になる。「帰宅すると危険がある」「居所がない」場合には、医療機関が本人とともに緊急一時保護の相談をすることもできる。相談窓口には守秘義務があり安全が確保される。その他保護命令や自立への生活保護、母子支援(母国の福祉が乏しい場合特に説明を要する)、離婚や在留許可などの法律相談と必要な段階に応じて継続して支援の手がさしのべられる。
DV法と超過滞在者の対応
DV法に関連し、警察庁H20 年1月11日付通達(*3)や入国管理局への法務省H20年7月10日付通達(*4)では、被害に関する相談や被害者の在留資格には事情を配慮するように記されている。在留資格に問題(超過滞在や在留資格更新時期など)を有する被害者は、まず自治体DV相談窓口の相談員が被害者のDVに関する真の事情を聴取し、DV証明書(内閣府H20年5月9日通知(*5))などを使い段階を経て総合的に問題解決することを勧める(残念ながら警察や入国管理局はDV法の専門家ではない。)DV法の目指すものは、被害者に在留資格を問わない福祉、医療制度(日本国籍の子への支援制度等も含め)を利用し被害からの回復と人生の再出発を支援することである。
*1 内閣府男女共同参画局 http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/dvhou.pdf
*2 自治体の例:神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/jinkendanjo/dvsien/、内閣府 http://www.gender.go.jp/e-vaw/book/02.html
*3,4,5 内閣府 http://www.gender.go.jp/e-vaw/kanrentsuchi/index.html
文責:特定非営利活動法人 女性の家サーラー理事 新倉久乃
機関誌「Bon Partage」No.146(2010年1月号)掲載
Donation すべての人と健康を
シェアする活動を、
毎月の寄付で
応援しませんか?
シェアは、いのちを守る人を育てる活動として、保健医療支援活動を現在
東ティモール・カンボジア・日本の3カ国で展開しています。
- 寄付で応援する(support/donation/index.html)
寄付で応援する
マンスリーサポーター、
一回のみの寄付、
遺贈による寄付などが可能です。 - モノを集めて、 モノを購入して支援(support/mono.html)
物の寄付で応援する
書き損じハガキ、未使用の
はがきや切手、商品券、使用済みの
切手による寄付が可能です。 - ボランティア・インターンとして参加(support/volunteer/index.html)
参加して応援する
スタッフ、ボランティア・
インターンとしてシェアに
参加することが可能です。