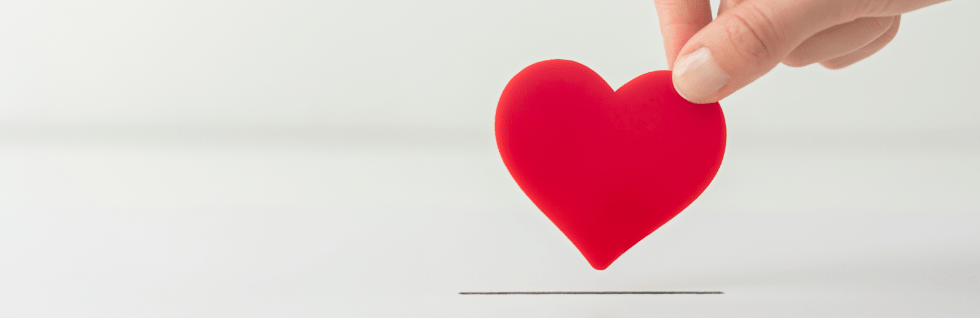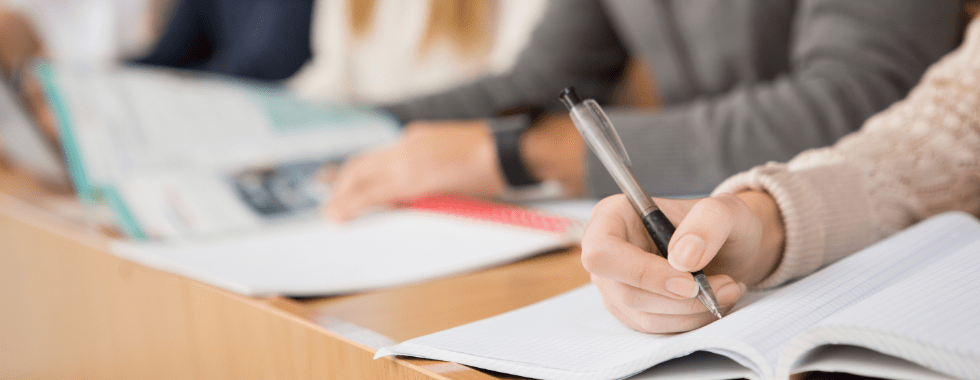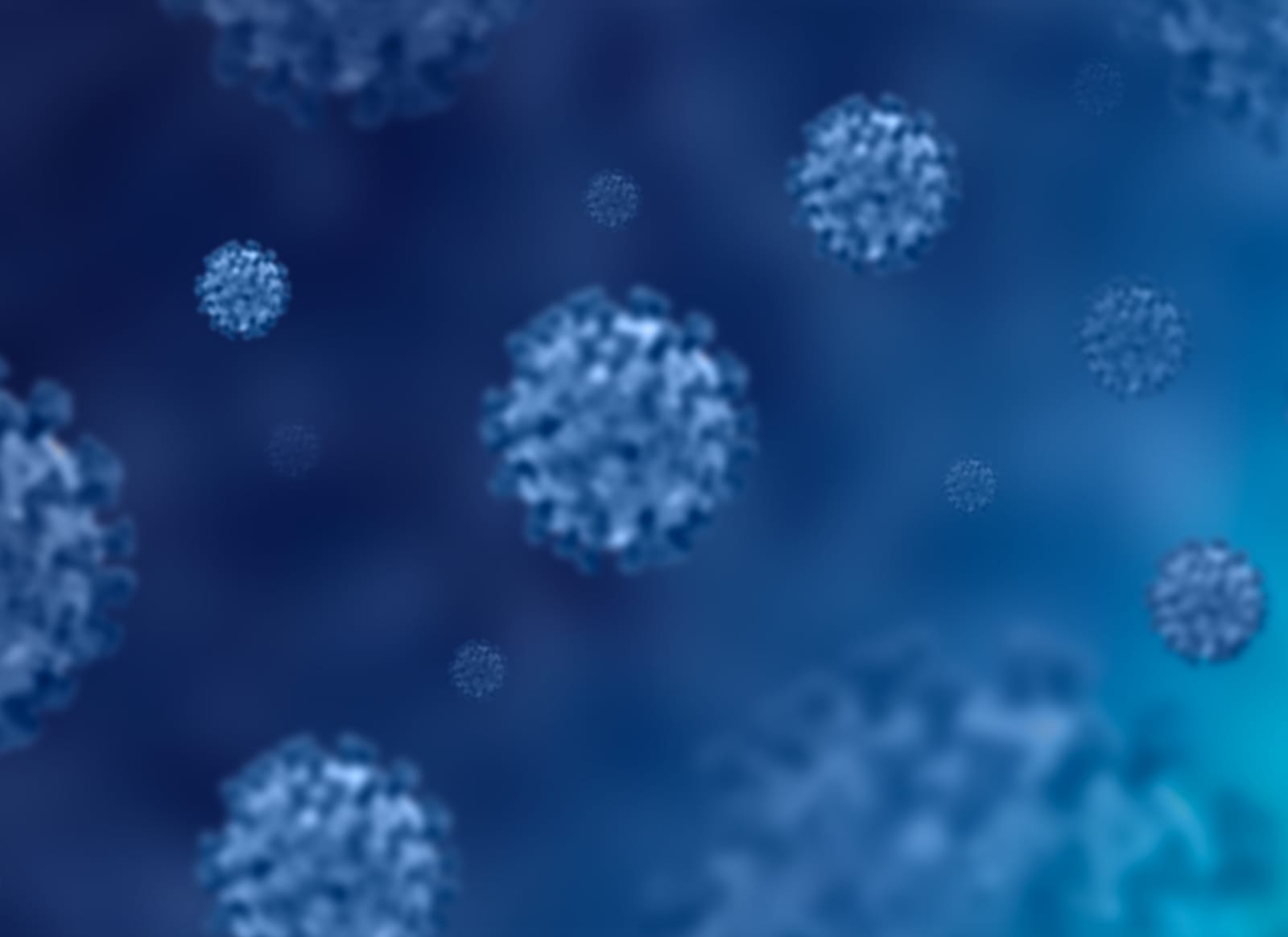感染症とは
-
感染症とは[顕性感染]
感染により起きる症状が、患者自身の自覚や、医師・看護師の臨床的観察・確認で、病気の状態であると判断されたもの。
-
新興感染症
新たに流行した・以前に発生したものが、頻度が増えたり、地理的・媒介虫・発生者の範囲が拡張したりする感染症。
感染とは、人間や動物の体内にさまざまな病原体が侵入し、発育・増殖することを言います。感染を起こす病原体には、プリオン、ウイルス、細菌、真薗(かび)、原虫、寄生虫などがあります。感染症は、感染によって起きる症状が、患者さん自身によって自覚されたり、医師や看護師によって臨床的に観察・確認され、病気の状態になっていると判定されたものを指します。これを顕性感染と呼びます。ただし、不顕性感染の中にも、HIV感染症、C型肝炎のように、潜伏しながら、れっきとした病気としての振る舞いをし、進行をしていくものがあり、十分な注意を要します。近年では、WHOにより、新しく認識された、新たに流行した、以前発生したものが、頻度が増えたり、地理的、媒介虫、発生者の範囲が拡張した感染症と定義されている「新興感染症 Emerging Disease」が世界の脅威となっています。エボラウイルス病、新型コロナ感染症や三大感染症としてのHIV感染症、マラリア、結核などが含まれます。
感染の経路
どのように病原体がヒトからヒトへ、また、動物とヒトとの間で移り、広がっていくか
- 空気感染
- 飛沫感染
- 接触感染
- 経口感染
- 媒介動物感染
- 性行為感染
- 血液感染
感染症について適切な予防対策を行っていく上で大切なのは、どのように病原体がヒトからヒトヘ、また、動物とヒトとの問で移り、拡がっていくか、という感染経路に関する認識です。主なものに、空気感染、飛沫感染、接触感染、経口感染、媒介動物感染、性行為感染、血液感染があります。空気感染は、患者さんの咳やくしゃみと一緒に放出された病原体を、近くにいる人が吸い込むことで成立します。
空気感染として代表的なのは、結核菌やレジオネラ菌のように、水分を失った飛沫核の状態でも空中に長く漂って感染力を保持する病原体です。飛沫感染では、インフル土ンザ・ウイルスや新型コロナ・ウイルスのように、水分の多い飛沫に含まれて短距離を移動し、感染するする病原体です。接触感染は、院内感染で有名になったMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)に代表されるように、ヒトの手指や器具などを介して感染するものやエボラウイルス病などの人間の体液に触れることによる感染するものです。経口感染は、汚染された食物や水の中の病原体が、口から消化管に侵入して起きるものです。O-157などの病原性大腸薗、A型ウイルス肝炎などが有名です。媒介動物感染は、節足動物が病原体の運び屋(ベクター)となって移るもので、マラリア原虫や日本脳炎ウイルスを運ぶ蚊、ペスト薗を運ぶノミなどが代表的です。現代の最も重要な性行為感染症はもちろんエイズです。
感染症の歴史と現在
-
人類誕生〜
「傷寒論」「旧・新約聖書」「ヒポクラテスの医書」等、世界中の古典にも感染症の記述がある。
-
19世紀中葉
感染症の原因が病原体であることを洞察していたゼンメルワイズの業績は偏見や権威主義の強い医学界で圧殺された。
-
19世紀後半〜現在
パスツールやコッホらにより、感染症が肉眼では見えない病原体に起因するものだという認識が社会で認められた。
人類は誕生以来、ずっと感染症と付き合ってきました。後漢の時代の「傷寒論」、ヒポクラテスの医書、旧・新約聖書など、世界中の古典に、さまざまな感染症によって苦しむヒトの姿が、生き生きと描かれています。しかし、何百万もの人命を奪う感染症が、肉眼では見えない病原体に原因するものだという革命的な認識を、人類がもつようになったのは、顕微鏡や細菌培養法やワクチン技術の開発・実用化によるもので、19世紀後半のパスツ一ルやコッホらの仕事を待たねばなりませんでした。
感染症とのたたかいは、病原体とのたたかいであるとともに、時代や地域を越えて遍く人間社会に存在してきた、偏見や権威主義とのたたかいでもありました。細菌学が確立される直前の、19世紀中葉のヨーロッパで先駆的な感染症対策の仕事をした、ゼンメルワイス(1818-65年)というハンガリー人産婦人科医がいます。分娩の前後、産道から病原菌が侵入して起きる産褥(さんじょく)熱が、当時猛威を振るっていて、致死率も高く、施設出産は女性にとって命がけのことでした。ゼンメルワイスは、医学生が分娩介助する、ウィーン大学病院の産院第一クリニックでの産褥熱による死者が異様に高いことに注目します。たとえば、1846年には第一クリニックでの死亡率は12%近く、一方、助産婦が分娩介助する第ニクリニックでは2%ほどでした。彼は、医学生が死体解剖実習の後、服も着替えず、手も洗わず分娩介助に直行していることが間題だと考えます。医学生が持ち込む「死体由来の感染粒子」が産褥熱の恐ろしい流行を起こしていると洞察した彼は、分娩室に入る前に、塩化石灰水で手指を入念に洗うようすべての医学生・医師に義務付けます。「手洗い」という当時としては前代未聞の予防的介入が始まった1847年以降、第一クリニックの産褥熱患者は激減し、第ニクリニックと同じ水準となります。
しかし、彼の業績は、医学界で圧殺され、彼は失意のうちにウイーンの精神病院で死にます。現代の院内感染の筆頭格、MRSA感染症の主要な「犯人」は医師の手であるということは、いくつかの調査で証明されており、ゼンメルワイスの原点に帰って医師たちは深刻に反省しなければなりません。
今後の課題
感染症は、病原体、ヒト、動物、環境との間の複雑で有機的な関係の中で起き、拡がります。現在、移動手段としての航空機の普及により、新型コロナ感染症のような新興感染症が瞬く間に世界に広がり、多くの犠牲者を生み、世界規模の課題となっています。
これまでは、感染症は、低所得国における課題と考えられてきたが、新型コロナ感染症の世界規模での流行により、欧米の高所得国における犠牲者がより多く、世界の国々が協調して対策にあたることが必要となっています。感染症対策の基本は、手洗いを中心とした予防活動が大事ですが、科学的な根拠に基づいた検査・診断・治療、リスクコミュニケーションを含めた公衆衛生対策をする必要があります。
同時に、感染症にかかった人に対する根強い偏見・差別とスティグマ(患者に罪を負わせる烙印)を取り除く努力を、社会全体がもっと真剣に行っていかねばなりません。
シェアのイベントに参加してみませんか?
シェアの感染症に関するプロジェクト
シェアの感染症に関するプロジェクトはありません。