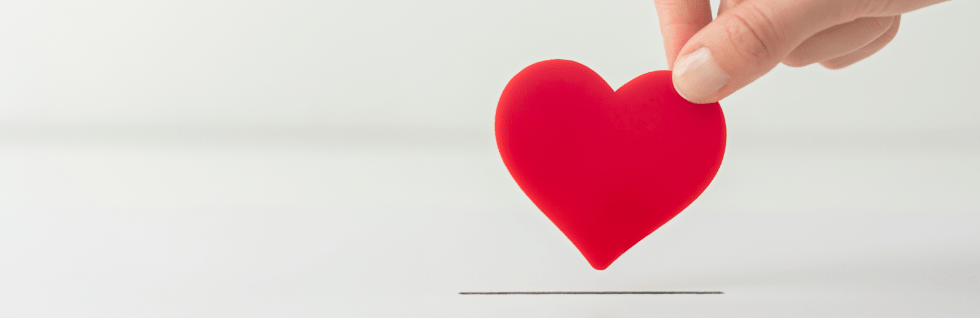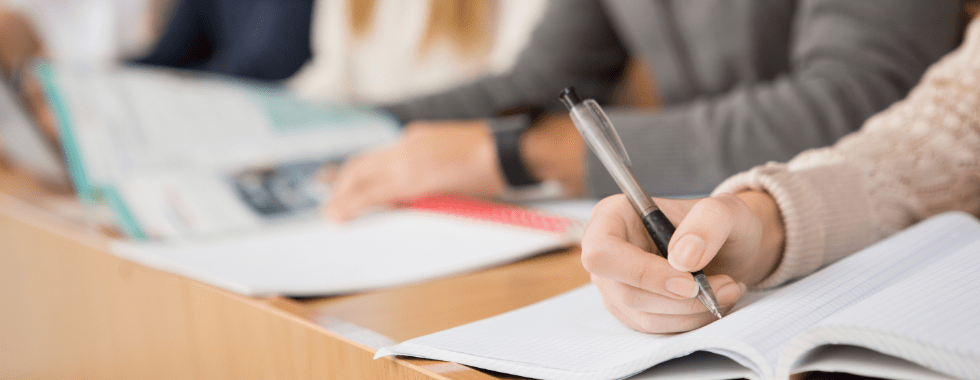《主張します》外国人母子が安心して保健医療を受けられるよう 国・自治体の取り組みが進むことを望みます
シェアが主張すること
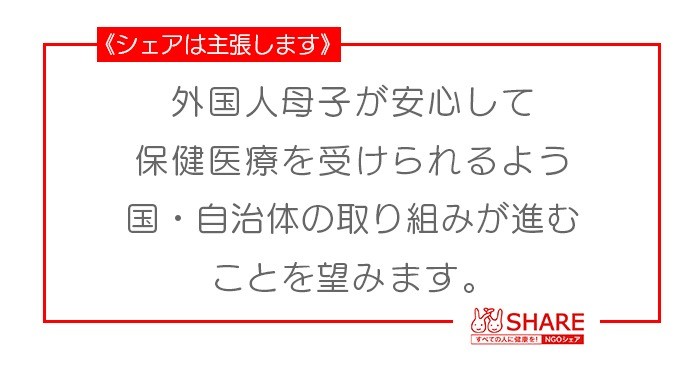
外国人母子が安心して保健医療を受けられる環境を目指して
シェアでは、1991年から日本に住む外国人の健康支援活動を始め、2016年からは外国人母子を対象とした活動を開始しました。2023年に作成した中期計画の今後の方向性の一つとして、アドボカシー活動を掲げました。アドボカシーの目的は、人々の広い意味での「健康」にかかわる課題、特に、シェアの実際の活動の中で見出した、保健制度、人権、紛争などの課題について、政府・地方自治体などに働きかけ、その改善を促し、同時に、市民・地域住民に問題点を提起し、市民一人ひとりの意識化や、市民からの制度への働きかけに繋げるものです。シェアでは、これまでの外国人母子への活動を通して、自治体等の保健医療福祉従事者、コミュニティの人々、医療通訳者から様々なことを学ぶと共に、国籍問わず日本に住むすべての人が安心して生活していくには、現在の制度では十分でない部分も感じてきました。特に、国、自治体の取り組みとして、公的な医療通訳体制の整備等の必要性を実感しており、今回以下の提言文を作成しました。
代表理事/事業部長 仲佐 保
*******
1)公的な医療通訳体制の整備
2)多言語資料と情報提供体制の充実
3)基本的な母子保健サービスの提供の徹底・保健医療福祉従事者等の学びの機会の提供
日本に住む在留外国人は年々増加の一途をたどり、2024年末には全国で376万8977人*¹と過去最多となりました。日本全体の出生数が減少する一方、日本で出産する外国人数は年々増加し、日本で生まれる子どもたちの約25人に1人*²は、両親のどちらか、あるいは両方が外国人です。日本で妊娠・出産・子育てを行う外国人世帯が今後ますます増加すると考えられる中、日本に住む外国人妊産婦や母子、家族の多くが、言葉の壁や母国と日本の保健医療システムや文化の違い、制度等、様々な要因により、本来受けられるはずの母子保健サービスにアクセスできていない状況が長年続いています。また、こういった外国人妊婦や母子と関わる保健医療福祉従事者の多くが、外国人妊産婦や母子にも日本人と同様に、相手の状況や気持ちを理解し、ニーズに沿った納得のいく支援を行いたいと思うものの、言葉の壁等により行えず、もどかしさを感じている現状もあります。
そういった中、シェアでは、2016年から自治体を中心とした保健医療福祉従事者等と連携して母子保健活動を行っています。活動の中で力を入れているのは医療通訳の活用促進で、自治体や医療機関の保健医療福祉従事者からの依頼に応じ、妊婦健診や乳幼児健診、赤ちゃん訪問等の基本的な母子保健はもちろん、妊娠中から生まれてくる子どもの養育環境を整えていく必要がある特定妊婦の支援や、子どもの発達や医療的ケア児の支援、時にはDVケースの支援まで、様々な場面へ医療通訳を派遣しています。
医療通訳を活用した保健医療福祉従事者からは、医療通訳を活用することで、「これまで聞けなかった妊産婦や家族の状況や困り事、気持ちの細かなニュアンスまで把握することができ、必要な支援につなげることができた」「医療的ケアが必要な子どもの困りごとは自己責任で対応するしかないと考えていた家族が、通訳を活用して関わるうちに、困った時には保健師に相談して良いと理解され、早めに相談してくれるようになった」等の感想が聞かれています。
医療通訳の活用により、保健医療福祉従事者と外国人妊婦や母子・家族の双方の理解が深まり、信頼関係の構築、切れ目のない支援につながっていると感じています。
また、活動を行う中で、母子保健分野では、保健医療福祉従事者からの説明や情報提供が中心となる場面だけでなく、妊産婦や家族の状況や気持ちを聴くことが大切となる場面も多く、通訳者がそばにいて、妊産婦や母親が安心できる話しやすい雰囲気を作りながら、妊産婦や母親と保健医療福祉従事者の双方に寄り添いながら関わることのできる「対面での通訳」が求められていることも分かってきています。
その他、基本的な母子保健サービスに関しては、本来、国籍や在留資格・健康保険の有無によらず利用できるものの、現場には十分伝わっておらず、保健医療福祉従事者が対応に困り、自治体によりサービス運用にバラツキがみられている現状もあります。例えば、住民基本台帳に載らない3か月以内の在留資格(短期滞在)の外国人や在留資格のない外国人は、居住実態があるにもかかわらず住民ではないとみなされ、母子保健サービスの対象とならないこともあります。2015年に世界の共通目標として国連で採択されたSDGs では「誰一人取り残さない(Leave no one behind)」が謳われており、保健医療は目標3「すべての人に健康と福祉を」として重要な項目とされています。どの地域においても、すべての人に母子保健サービスが公平に提供されることが望まれます。*³
このような支援現場の状況に鑑み、シェアは、保健医療福祉従事者が外国人妊婦や母子、家族にも納得のいく支援を提供できるよう、そして日本に住む全ての妊婦や母親、家族が、必要な母子保健サービスにアクセスでき、日本で安心・安全・健やかに出産・子育てを行っていけるよう、以下のような主張をします。
1)公的な医療通訳体制の整備
言葉の壁を解消し、保健医療福祉従事者等が外国人妊産婦や母子、家族と、相互理解を深めながら、必要な支援やサービス等を活用するには、様々な場面で「日常的に医療通訳を活用できる環境」が整うことが必要であり、公共サービスとして医療通訳制度が構築されるべきだと考えます。また、対面通訳とオンライン、電話通訳など、状況や内容、タイミングにより通訳ツールを使い分け、対象者の状況や気持ちをしっかり把握する必要があるような場面では、対面での通訳を活用できることも必要だと考えます。通訳費用に関しても、多くの先進国は、利用者が負担するのではなく、国や自治体が負担する形で、公共サービスとして提供されており、日本においても同様に、利用者は経済的負担を感じることなく言語的不利益が解消されるべきだと考えます。
2)多言語資料と情報提供体制の充実
外国人妊婦や母親・家族に必要な情報が届くよう、外国人が理解しやすい内容で、かつ現場の保健医療福祉従事者が活用しやすいよう、広域で活用できる多言語資料の整備が必要だと考えます。また、外国人住民がアクセスしやすい場所やSNSなどを利用した情報発信、電話番号を持っていない外国人住民も多い中、電話だけでなくインターネット等を利用した多様なコミュニケーションツールを活用するなど、「情報提供体制の充実」を社会全体として進めていくべきだと考えます。
3)基本的な母子保健サービスの提供の徹底・保健医療福祉従事者等の学びの機会の提供
厚生労働省からの正しい情報が各自治体等に十分伝わり、基本的な母子保健サービスが、国籍や在留資格・健康保険の有無によらず、自治体等により運用に差が出ることなく提供されることが望まれます。
また、保健医療福祉従事者等が、外国人母子支援に取り組みやすくなるよう、諸外国の文化や在留資格、困難ケースの対応経験や各自治体や施設での取り組み等をお互いに学び、連携を深めていけるよう「外国人母子支援時に必要な知識・情報の習得の機会の充実」が重要だと考えます。国や自治体等が積極的に関係者の学びと情報交換の機会を政策として企画運営してゆくと望ましいと考えます。
-------------------------------------------------------------------------------------
*¹ 出入国在留管理庁 報道発表資料 「令和6年末現在における在留外国人数について」(2025年3月14日)より。
*² 国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2024)」より。
*³ 外務省 JAPAN SDGs Action Platform (https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html#about_sdgs)より。
*******