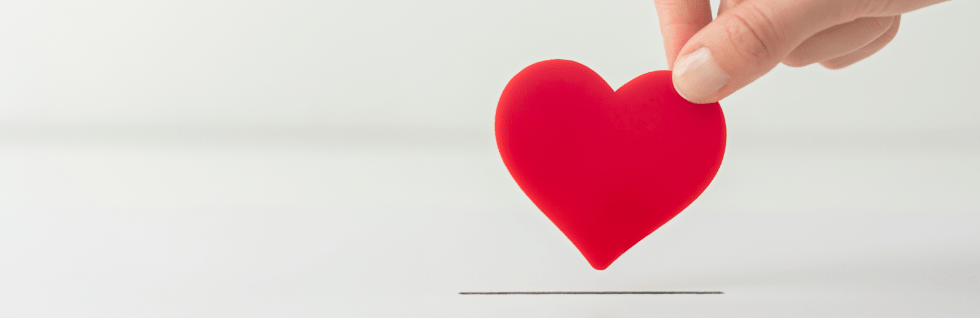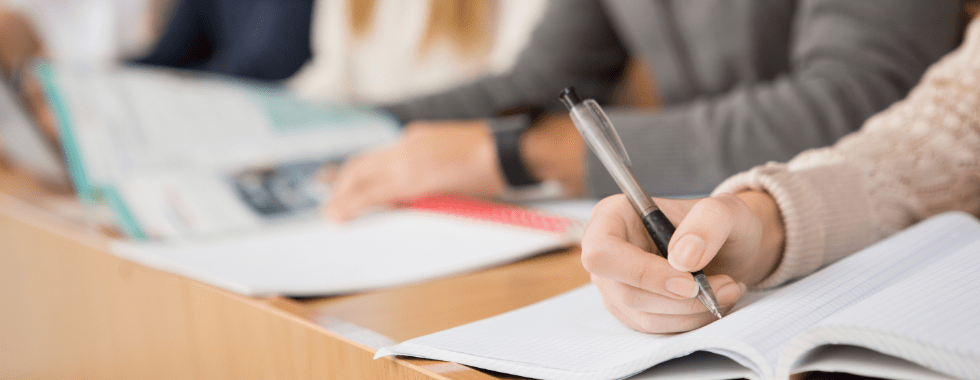【在日外国人支援事業ブログ】女性普及員とともに、久しぶりの妊産婦訪問に行ってきました!
- 医療通訳者や保健ボランティアと共に妊産婦や母子の健康をまもる
- 在日外国人支援

こんにちは!在日外国人支援事業を担当している山本裕子です。
シェアは、2017年頃から、女性普及員(Female Health Promoterと呼んでいるネパール人保健ボランティア)を育成し、彼女たちと一緒に妊産婦宅を訪問し、日本の母子保健サービスの説明や、妊娠中や産後に行う手続きの説明を行うとともに、妊産婦が困っていることなどの相談に乗り、必要に応じて担当の保健センターなどに橋渡しを行うなどの活動を行ってきました。
ここ数カ月、シェアスタッフと女性普及員たちのタイミングが合わないなどの理由で行えていなかったのですが、久しぶりに、6月28日に妊産婦訪問を行いましたのでご報告したいと思います。
対象地域に住んでいる妊婦宅訪問
今回、訪問した妊婦さんは、最近日本に来た方ばかりの方でした。妊娠28週で、以前流産を経験されていました。居住地は、シェアが対象地域としている都内10区の1つで、普段より、母子保健場面での医療通訳の依頼をいただく総合病院での出産を予定されていると分かり、何かあればシェアからもつながりやすいと安心しました。出産予定の病院では英語が話せる医師がいるということで、安心感があるようでした。
いつも通り、女性普及員のほうから、日本の母子保健サービスや手続きを一通り説明しながら質問に対応しました。出生連絡票(出産後に郵送するはがき)の書き方を説明した際は、夫が自ら、後で消せるように鉛筆で、どこに何を書くべきか直接はがきにメモを取るなど、積極的に行動してくれていました。それを見た女性普及員たちは喜んでいました。妊婦さんは、過去の妊婦健診で尿糖が+と出るなど、妊娠性糖尿病の可能性があり、最近、食前と食後の血糖を測る指示が出ていました。
妊婦さん(右端)たちに母子保健サービスなどについて説明している女性普及員(左端の2人)
一通り、保健センターからもらっている書類を確認し、必要そうなものを、通訳を交えて説明していきました。この夫婦は、陣痛が来た時には、救急車を呼べると思っていたようで、通常は呼べないと知り心配になったようでしたが、陣痛タクシーの存在を伝えたら安心されていました。また、子育てハンドブックのような、日本語で書かれている、いろいろ情報が得られる冊子類についても、どんなことがかかれているかを説明し、必要なら読んでみて、と伝えると、スマートフォンで翻訳して読んでみる、と答えるなど、この妊婦さんは積極的に興味を持って調べる方だと感じ、この妊婦さんなら安心だな、と感じました。
担当の保健センターで行われる母親学級にも参加するように言われていると行く予定にされており、またシェアが行うネパール語のオンライン母親学級にも参加したいということで、また5日にお会いしましょうとお伝えしてお別れしました。
訪問後、女性普及員から聞かれた感想としては、
「母子手帳の重要さなど、自分たちが妊婦さんに伝えたいことが伝えられてよかった。」
「夫婦共に日本語があまりできないみたいで、英語ができる医師がいる病院に行ってはいるが、わからないところも多くあったので、今回訪問できてよかった。」
「まだ受けられていなかった、歯科健診の早期受診を勧められてよかった。」
など様々な声が聞かれました。
妊娠中に一度訪問した産婦さん宅訪問
同じ日の午後には、昨年私たちが妊婦訪問を行った、現在生後3か月の女児を育てる母親宅を訪問しました。このお母さんは、妊娠中にシェアが開催したオンライン母親学級にも参加してくれました。今回訪問したところ、帝王切開の予定日より早く破水が来てしまい帝王切開が早まったことや、出産後2カ月は初めてなので心配事も多かったが、落ち着いてきて、今はいらない心配だったと思う、などと話してくれました。赤ちゃん訪問も保健センターの方が来てくれたようでした。

お母さんの産後の生活などをお聞きしている様子
赤ちゃんは、夜も4時間ぐらいは寝てくれるため、よく寝てたら起こしてまでミルクを与えなくて大丈夫ですよね、とちょっとだけ心配そうに聞いて来られる場面もありました。“何時間おきにミルクを飲ませる必要がある”というような枠から外れることに少し不安を抱いていたのかなと思いました。
赤ちゃんはとても穏やかに過ごせていて、一度ミルクを与えている姿を拝見しましたが、泣き続けるわけでもなく、抱き続けなくても大丈夫な印象があり、初めての育児も一番大変な時期を脱したのかな、と感じました。
来年度から職場復帰を考えており、保育園の費用など心配されていたので、来月行く予定にされている3-4か月児健診で、質問してみてはどうか、と伝えました。
予防接種も受けられているようですし、しっかり母子保健サービスを受けられていて、妊婦訪問や母親学級で情報提供してきた効果を実感することができました。この方のように、ケースバイケースにはなりますが、母親学級と妊産婦訪問を組み合わせて支えていけることは理想的だなと感じました。
※この活動は、2025年度立正佼成会一食平和基金の助成、WE21ジャパン厚木の助成、皆様からの寄付などのご支援で実施しました。


東京事務所 在日外国人支援事業担当
山本裕子