HOME > シェアが主張すること > 沢田貴志 「健康に生きる権利」の揺らぎ
沢田貴志 「健康に生きる権利」の揺らぎ
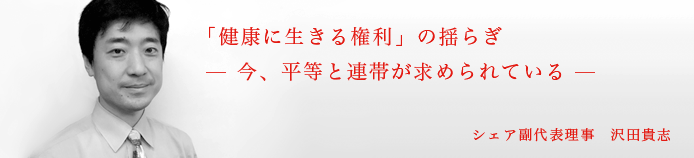
健康を実現するのは医療だけがあればよいのではありません。生活環境や労働環境、栄養や情報など日常的な生活基盤の安定こそが重要です。しかし、果たしてそうした基礎的な社会資源が、現在の日本に生活する人々に等しく享受されているでしょうか。2008年7月に発表された人口動態統計には、ショッキングな統計が示されています。在日外国人、特に女性の年齢修正死亡率が、日本人に比して非常に高く、外国人女性の死亡率は日本人女性よりも26.7%も高いのです。もはや途上国と日本との間にあった健康格差は、日本国内の階層格差として現実のものとなろうとしています。
風化する健康権
私たちが戦後の日本社会の中で守ってきた大切な理念の一つに、「すべての人が平等に尊重されるべき」という考え方があります。平等に医療を受ける権利は、公的医療の向上と、健康保険制度の確立の中で揺るぎないものとなり、日本の平均寿命を世界一に押し上げました。平等な医療や福祉へのアクセスは社会の安定に役立ち、平和で安全な社会の原動力になったと言えるでしょう。ブラジルやタイでは、1990年代から医療の格差を減らし、住民の健康を守る事が社会の安定と成長に貢献するとの考えが力をつけ、公的医療の整備が進みました。こうした中開発国の間で、日本型の医療保障制度を取り入れる動きが進むなかで、日本では逆に、社会保障の後退が続いているのです。医療にかかれない外国人の増加
ここ数年の政策転換の中で、保健医療サービスに経営効率を求める考え方が導入され、公的医療機関すらも独立採算性が求められるようになりました。その結果、健康保険を持たない外国人が、真っ先に医療から振り落とされています。1990年代初頭、外国人人口が急増しました。多くの公立病院では、健康保険を持たず医療費の払えない外国人に対しても、人道的な立場から救急医療をまず提供し、その後に、医療費の回収努力をしていました。しかし、ここ数年の傾向として、医療費を払えそうもない外国人患者の場合、診療を回避しようとする医療機関が増えています。
私たちの課題
こうした外国人への診療忌避は、「命の平等」という理念にほころびを生まれさせ、日本人への診療拒否に拡大して行く可能性があると、私はこれまでも指摘してきました。いまや、健康保険料滞納のために保健証を差し止められている子どもが3万人、健康保険料を支払えない高齢者や貧困世帯が医療を受けられないといった懸念が現実の問題として議論されるようになりました。日本国憲法が保障した「健康で文化的生活をする権利」が経済の論理によって揺らいでいるのです。不健康が自己責任であるかのような論理が急速に力をつけ、効率的に医療を提供するためには、多少の痛みはやむを得ないという声がこの国で受け入れられようとしています。この論理を乗り越えるために私たちに何ができるでしょうか?
格差ではなく平等が、排除ではなく連帯が健康作りの要
私たちが途上国、カンボジアやタイ、そして東チモールや南アフリカで学んできたことは、住民参加の手法ですべての人に平等な医療を提供することこそが、最も効率的に地域の健康を実現するのだということです。格差ではなく平等が、排除ではなく連帯が健康作りの要なのです。もちろん、説得力をもってこの事を日本社会に伝えてゆくことは容易なことではありません。国内の活動や海外の事業を通じて、その具体例を示して行くとが、シェアに求められていることだと考えます。
シェア=国際保健協力市民の会 副代表理事 沢田貴志
(20108.3)
(20108.3)


